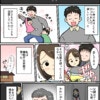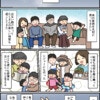©ママリ
©ママリ
私が妊活中とわかっているのに妹が先に第二子を妊娠「聞いていた話と違う」騙された
 ©ママリ
©ママリ
家族の幸せを喜べない自分が嫌で苦しいです。
私は現在不妊治療2年目です。年齢的なこともあり焦りが出ています。
妹は不妊治療で1人目を授かり、姪っ子は今一歳です。
不妊治療中に転職をし、その後妊娠。良い会社で現在育休2年目。
私は旦那の転勤があり、正社員で長く勤めた会社を辞めてフルタイムパートで転職。その後不妊治療を始めましたが、休み申請のたびに嫌な顔や嫌味を言われ、ストレスが多くさらに自然妊娠した子を流産。
旦那と相談し、退職→現在別の職場で扶養内パートをしています。
半年前から体外受精を始め、着床しますが育たず流産してしまいます。
収入も減り、さらに育休も取れないのでお金の不安はありますが、「お金は後から取り返せる。今は不妊治療を優先しよう」と思っていました。
去年妹に不妊治療やお金の相談をしたところ、「私も将来のお金が不安だ。だから2人目は考えていない」と言っていました。
私の上記の考えにも「良いと思うよ!」と言っていました。

現在不妊治療中のSさんは、フルタイムパートで転職。1人目を自然妊娠したものの流産してしまった経験もあります。お金の不安があるものの、後で取り返せるという気持ちで不妊治療を優先させて過ごしています。
Sさんには妹がいます。妹は1人目を不妊治療で妊娠し出産しています。その後Sさんには「2人目は考えていない」と話していたそうで、Sさんを応援してくれている様子の妹。Sさんも前向きにがんばろうと思っていたように感じられます。
「聞いていた話と違う」
気が変わって、また治療しているとのこと。
驚きましたが、能天気バカな私は「じゃあお互い上手くいったら子ども同級生だね!」と話したところ、妹からは「お姉ちゃん、私が先に妊娠したら嫌?」と言葉が返って来て、ものすごく不快な気持ちになってしまいました。
しばらく妹とは距離を置いて、家族LINEグループ(しょっちゅう姪っ子の動画や写真が送られて来ます)も既読スルーしていました。
ですが、最近妹からLINEが来ることが増え、やり取りが再開しました。
LINEの内容は「来年職場復帰のために保活をしている。保育士の姉に良い保育園選びのアドバイスをもらいたい」という内容でした。
復帰せず2年育休だけとって辞めるのかと思っていたので、あれ?と思いましたが、デリケートなことは何も聞かず質問に答えアドバイスをしました。それが先月の話です。
なのに、今日2人目妊娠報告。1月出産予定で、職場は3年目育休を取るそうです。
不妊治療がうまくいかない私と2人目の妹。
育休が取れない私と3年も取れる妹。
比べてしまって妬ましく、辛いです。
さらに、「聞いていた話と違う」と、騙されたように感じてしまいます。

2人目は考えていないと言っていたのに、気が変わって不妊治療を始めた妹。
来年職場復帰するからと相談してきていたのに、2人目妊娠報告からの3年目育休を取る予定の妹。
一方、不妊治療はうまくいかず、たとえ妊娠しても育休が取れないSさん。
今の自分と妹の環境や立場を比べ、妹を疎ましく感じてしまうSさん。家族の幸せなのに喜べない…どんどん理想の自分とかけ離れていっているように感じてしまい精神的にとても追い詰められているように感じます。
妬みたくないのに妬ましい自分が嫌になる
私だって妬みたくありません。
旦那は「出産祝いだけ郵送で送って、またLINE既読スルーで距離をおけば良い」と言いますが、私は出産祝いすら送りたくない気持ちでいっぱいです。
あんなに可愛かった姪っ子も、今は可愛く思えません。
妹に「もう私に連絡してこないで!」と思ってしまいます。
家族の集まりにも参加したくありません。
こんな自分が嫌になります。
2人目フィーバーの家族LINEから退会したいくらいですが、家族仲良いため退会しずらく、ふとした時に見えてしまいその度にもやもや。
この感情をどうしたら良いのでしょうか?
また、家族を悲しませずに妹と距離を取りたいのですが、みなさんならどのように距離を取りますか?
苦しくて苦しくて、助けていただきたいです。

Sさんの投稿には下記のような寄り添い、励ましのコメントが多数届きました。
それなら自分の幸せの感じ方を変えよう、ハードルを下げようとした方が簡単で効果的でした☺️
小さな幸せを見つけていたらいつの間にか、病弱とは言えご飯は食べられて寝たきりではない自分の体と、優しい夫と、大切な子供が一人居て、趣味に打ち込む時間や気持ちの余裕が産まれて、これで満足だなと思うようになりました☺️
目の前に理想の家族像をお持ちの方が居るので今すぐに気持ちを切り替えるのは難しいと思います。
ですが、気持ちの持ちようで幸せは幾らでもやってくると思います✨

だから主様の感情に同情します。仕方ないです。
言えるのは時が経ち冷静になったらいま抱いている感情は必ず解決されます。
自分だったらいまはご主人の言う通りで最低限出産祝い送るだけして
家族LINEは見ないかもです。

相手が誰であれ、羨ましい、妬ましいと感じることは誰にも一度や二度経験があると思います。負の感情を抱くことは自然なことであり決して悪いことではありません。
大切なのはその感情を否定するのではなく、どのように向き合い折り合いをつけていくか?といった部分なのかもしれません。自分の気持ちを大切にできる環境を、時には周りに頼りながら作っていけるといいですね。
産後に里帰りしたら「両親が超険悪」気になって涙が止まらない女性に、励ましの声


初産で里帰り中です。
帰ってきたその日から、両親が口をきいていないことに気付きました。
幼少期からケンカが多く、長女の私は両親の関係にものすごく敏感で、口をきいていないことにすぐに気付いてしまいます。
気にしなければいいのですが、せっかく赤ちゃんが来たのに家の中の雰囲気が最悪で、本当にストレスです。
産後のメンタルも後押しして母親に問い詰めると、私が陣痛で苦しんでいる時に父親が女とLINEしているのを見てしまい、キレたと話してくれました。
産後の一番大変な時に申し訳なくて、私には話さないでおこうと思った、と母親は言ってくれました。
でも怒りでとてもじゃないけど父親と普通に接することができないそうです。

初めての出産を経て、退院後に実家に着くと両親がケンカをしていたことに気づいたMさん。
赤ちゃんを産んだことに加え、すでに始まっている育児のこともあり、本来なら自分と赤ちゃんのことだけ考えていたい状況の中、両親のことまで考えなければいけないのは本当に苦しいですね。
夫に話して早めに里帰りを終えて自宅へ帰ろうと思っています。
今までもたくさん大きなケンカをしてきて、そのたびに私も仲介したりしてなんとかなってきました。
ですが今回ばかりはどうにもならなそうです。
私はどうしたらいいのでしょうか…。
生まれた子を守るため、両親のことは気にしないで自分たちの生活を中心に考えたいのですが、今後いつ実家へ帰ってきてもこの雰囲気なのかと思うと涙が出ます。
暗い話ですみません…同じような方いませんか😢

Mさんは長女ということで、これまで両親のケンカもMさんが仲裁することが多かったそう。そうした過去の経験もあり、両親の仲を取り持つことにも疲れているMさん。実家の雰囲気が重いこともあり、早めの里帰り切り上げを考えています。
こうしたMさんの状況に、ママリユーザーからはどんな声が寄せられたのでしょうか。
これからは自分の家族を中心に考えればOKなどいろいろな声が
これまで、両親の中を取り持つことが多かったというMさんですが、今は初産を終え、自分のことでいっぱいいっぱい。とても余裕があるような状況ではありません。
そんなMさんにママリユーザーからはさまざまな声が寄せられました。
ほっときましょう!
ご自身でもおっしゃってますが、Mさんが考えるべきことはお子さんと旦那様のことです😊
実家に行って嫌な雰囲気を味わうくらいなら帰らなければいいと思います。

今まで両親のケンカを仲裁してきたMさんにとって、すぐに「両親のことは両親のこと」と割り切るのは難しいかもしれません。しかしこちらの意見のように、これからMさんが最も大事にする必要があるのは、自分がこれから作っていく家族のことです。
両親は両親、と腹をくくってどうかMさんも赤ちゃん、そして夫と心穏やかな毎日を過ごしてほしいですね。
また、Mさんと同様に産後に両親が不仲だった方からも体験談が寄せられていました。
それどころか父親は、母親と喧嘩中と思ってる気持ちが強くて、私や孫の事は二の次で、孫を抱きもしませんでした。
私はそれが嫌だったので、15日ほどで家に帰りました。
その後両親は離婚しましたが、母親は毎週の様に孫に会いに来ます。
父親は母親と離婚したショックで病んでますが、、、

こちらの意見では、父親の言動が冷たいもので、結局両親は離婚したようです。実母はその後も孫をかわいがっている様子ですが、実父は離婚でショックを受けている状態とのこと。家族の形態は各家庭でさまざまで、時には離婚を選ぶようなこともあります。しかし、それは両親の夫婦としての間柄の話であって、娘やその子どもが影響を受ける必要はないことですよね。
Mさんが自分の家族を大事にでき、心配ごとが早く解決するよう祈りたくなる投稿でした。
義父から「おかしい」と言われモヤモヤ…わが子に「ちゃん付け」するのは甘やかし?


私たち夫婦は、子どものことを○○くん、○○ちゃんと呼んでいます。
それに対して、自分の子どもを君付けで呼ぶことがおかしいと言われたそうで、モヤモヤしています。。
人に子どものこと話すときは君付けはしてないのですが、
甘やかせすぎと言われることなのでしょうか?
自分自身が、昔から親に○○ちゃんと呼ばれて育ってきたので、自然とそう呼んで育てていましたが、良くなかったのでしょうか😭

家族同士の呼び名は、各家庭でさまざまですよね。今回の投稿者は、わが子を「くん・ちゃん」付けで呼んでいるそうです。
投稿者自身も、実親からそのように呼ばれて育ってきたため、違和感なく過ごしていたとのこと。しかし、義父はそう思っていなかったようで、自分の息子である投稿者の夫に「甘やかしすぎ」と伝えたそう。
そのことを夫から聞いたのであろう投稿者はちょっとモヤモヤ…。孫の育て方について何かと口を出したくなる気持ちはあるうのでしょうが、ママリユーザーからはどんな回答が寄せられたのでしょうか。
呼び方は家庭それぞれ、気にしなくて良いのでは?
投稿者の相談に対し寄せられた回答には、「気にしなくて良い」という類いの回答が寄せられていました。
義父の世代からすると、「今の人は…」という具合の、何か気になることがあったのかもしれませんが、今、育児をしているのは息子世代なので、世代による今の事情もくんでほしいというのは正直な気持ちでしょう。
ただ、子どもを「くん・ちゃん」付けしているのは、今の世代というより、ずっと昔からもあった気がするので、呼び方をもって甘やかしすぎと言われるのはモヤモヤする気持ちも分かりますね。
家族内では、お互いを尊重する呼び方をしているのであれば、それは家庭の在り方としてそっとしておくのがベスト。1番大事なのは、呼び方よりも関わり方の中身なのではないでしょうか。