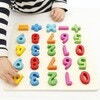幼稚園児から習い事は早すぎる?そもそも習い事は必要?
幼稚園に入園して、気になるのが幼稚園後や休日の習い事ではないでしょうか。幼児のうちからスポーツ系や勉強系の習い事に取り組み、子どもの能力を伸ばそうと思うママもいると思います。
中には幼稚園児から習い事を始めるのは早すぎるのではないかと感じているママもいるのではないでしょうか。幼稚園児の習い事は必要なのか。どんなメリットがあるのか。他のママの意見をご紹介します。
2歳8ヶ月からスイミング
4歳11ヶ月から学研教室(週2回、宿題あり)
6歳6ヶ月から習字(まだ、鉛筆の書き方のみ。宿題あり)
です。
楽器も検討しましたが、フルタイムワーママで練習させる時間がないので、楽器は習わせてないです。
習い事をさせるかどうかより、親が付き合えるかどうかがカギなように思います。テレビやスマホを見せてばかりになりがちですよね。。うちも宿題以外の時間はそんな感じです。習い事をさせたところで、親が構わなくていいわけではなくて、なかなか手間が増える感じです。手離れのいい習い事があればいいのですが、スイミングの1時間だけが「ママの1人時間」な感じです。

勉強系や音楽系の習い事で欠かせないのは宿題ですよね。まだ幼いうちは自主的にはなかなか宿題ができないので、親が見てあげなければいけません。その親の手間も考えて習い事を決める必要性がありそうですね。
○子供の様子
○先生は笑顔が多いか
○レッスン代
○休んだときの振り替えが出来るか
○駐車場は沢山停められるか?
○テストの頻度
○飛び級ができるか
を特に気にしながら探しました。
お友達同士の環境に関してはうちは全然気にしてませんでした。

習い事の内容はもちろんのこと、習い事のシステムや環境に目を配ることも親の大切な役目であると感じました。譲れない条件を書き出し、それに合致する習い事を見つけたいところですね。
他に頭の使い方が違うかもしれませんが、私は2歳からピアノを習っていました。両手を使って音を奏でることで頭の体操にもなるようです♪楽譜をよんだりお歌を歌ったり人と音を合わせることで協調性もうまれます。
それと一生書くことはついてまわるので書道もしていて良かったなと思っているので、私は子供に上記3つと何かスポーツを習わせたいなと考えています( ^ω^)
ちなみに書道は私はいまでもお稽古に通っています。

そろばん、ピアノ、書道は昔から続く人気の習い事ではないでしょうか。どれも集中力や頭の体操に良さそうに感じます。幼稚園の時だけでなく、生涯を通して、地域を問わず続けられる習い事というものもポイントが高いですね。
幼稚園児のどれくらいが習い事に通っているの?


幼稚園に通っている子どものうち、一体どれくらいの子どもが習い事に通っているのでしょうか。
0~2歳だけでも総合すると30%以上に達し、全体としては70%以上の家庭が4歳までに習い事を始めさせているのです。 ※1
就学前のお子様がいるご家庭を対象に実施した習い事に関するアンケート調査によると、3歳では23.2%、4歳では39.5%、5歳では51.0%が何らかの習い事をしていると回答したそうです。 ※2
統計によって結果はさまざまですが、株式会社やる気スイッチグループによると、4歳までに70%以上の子どもが何らかの習い事をしているようです。最近では赤ちゃんから始めることができるベビースイミングや、リトミック、親子での体操教室などもあるので、入園前から習い事を既に始めている子どもも多そうですね。
幼稚園から習い事をさせるメリットは?


幼稚園児の多くが習い事をしていることがわかりましたが、この幼児期に習い事をさせるメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
メリット1 コミュニケーション能力や礼儀作法が身につく


習い事では、普段通う幼稚園とは違った環境で過ごすため、コミュニケーションや礼儀作法を学ぶ機会にもなります。
幼児期の習い事では、礼儀やマナーも教えてもらうのが一般的です。したがって、知識を増やすだけでなく、先生の話に黙って耳を傾ける習慣が身につくなど、学習するためのベース作りを早めに行えます。 ※3
早いうちから集団で行動する機会を得る、先生の話をじっと座って聞くなどは、これからの成長の過程で役立ちそうですね。ほかにも、習い事先の教室で交友関係が広がるというメリットもあります。小学校に進級するときに、習い事がいっしょの友達がいれば心強く思うことでしょう。 ※4
習い事という、幼稚園とは異なる社会に属することで、そこに新しい人間関係が生まれます。先生や友人と習い事を通してコミュニケーションを行うことにより、だんだんと自分の意見を言うことができるようになったり、人の話を聞くことができるようになったりしていきます。
また、習い事の最初と最後には挨拶を行う、習い事の最中はきちんと座って先生の話を聞く、先生や目上の人には丁寧な言葉づかいをする、など習い事によってはマナーや礼儀作法が身につくことも期待できます。
コミュニケーション能力や礼儀作法は子どもの時から身につけておいて困るものではないので、親としてもうれしいですね。
メリット2 小学校入学時の自信になる


幼児期から習い事をすることにより、程度の差はあってもある程度その習い事に関する知識や能力が備わった状態で小学校に入学することになります。たとえば水泳を習っていれば、小学校の水泳の授業でスムーズに顔を水につけられたり、バタ足が上手にできたりします。お勉強系の習い事をしている場合、小学校での授業にスムーズに取り組めるかもしれません。
自分にとって自信が持てるなにかがある状態で小学校入学を迎えることは、その子にとってプラスに働くでしょう。
メリット3 感性が養われる


幼児期は、何にでも「なんで?」「どうして?」と興味を抱き、好奇心旺盛になってくるもの。そんな時期に、家や保育園、幼稚園以外の場所での刺激があれば、その興味はさらに大きなものになります。
この興味や好奇心こそが、自分の視野を広げる第一歩なのです。
自分で興味を持ったものを実際に見て、触れて体感することは、子供にとっては強烈な刺激となり、自分の世界が一気に広がります。 ※5
幼稚園児向けの習い事は、小学生や中学生向けの習い事とは異なり、五感を使った体験型の授業が多いのが特徴です。水泳はプールで遊んだり、泳いだりすることによってだんだんと水に慣れていきます。英会話では英語の先生とあいさつから初めて、英語の歌を歌ったり、手あそびを交えたりしながら英語に親しんでいきます。
筆者の4歳の娘が通っている音楽教室では、ピアノだけでなくさまざまな楽器に触れ、実際にどのような音が出るのかを楽しんだり、身体全体を使ってドレミの歌をみんなで歌ったりしています。
このような体験は好奇心旺盛な幼児期には大きな刺激となり、感性がどんどん豊かになっていきます。幼稚園とは異なる場所、人と過ごすことによってまだまだ柔らかい子どもの思考はより伸びやかになっていくように感じます。
幼稚園児向けにはどんな習い事があるの? 人気の習い事は?


それでは幼稚園児向けにおすすめの習い事はどのようなものがあるのでしょうか。人気の習い事をご紹介します。習い事で悩んでいるママはぜひチェックしてみてください。
水泳


男女ともに一番人気の習い事は「水泳」で、5歳で通っている子どもは全体のおよそ2割を占めています。水泳は全身運動なので運動神経や体力を養えますし、小学校に入学すると水泳の授業が始まりますので、それまでに泳げるようになってほしいというのが主な理由です。 ※6
昔から根強い人気を誇る習い事の1つが水泳です。全身運動である水泳は、泳ぐことができるようになるだけではなく、心肺機能を鍛えることができ、結果的に身体を強くすることが期待できます。
小学校では水泳の授業もあるので、幼児期から習っておくことで入学までに泳げるようになっておきたいという親の願いからも人気の習い事です。
また、他の習い事と比べて早い段階で始めることができるのもメリットの1つです。0歳や1歳からベビースイミングを始め、そのまま3歳、4歳になっても継続して習うことができるのもうれしいですね。
英会話、英語


2020年からは、英語教育が小学校3年生以降の学年で必修になります。また、ビジネスや進路のグローバル化の影響もあり、英語を早くから学ばせたいと考える親が増えました。英語塾はそのようなニーズを背景として、幼児への指導を熱心に行っているのが実情です。小学校で英語を勉強として教わる前に、言語として親しませておくことで、将来的に実践的な力として役立つことを見込めます。 ※7
これからより一層進むグローバル化に合わせて、2020年から小学校の英語教育が必修化されました。パパママが子どものころとは異なり、早い段階での英語教育のスタートに備えるという意味で英会話や英語が支持されています。幼いうちから英会話に慣れ親しんでおくことで、英語の授業や英語そのものへの苦手意識が軽減され、中学、高校と続く英語教育への自信につながっていくのではないでしょうか。
ピアノ、音楽教室


人間の聴覚がもっとも発達するのは、4・5歳のころ。
この時期にたくさんの音楽を聴き、歌い、弾く体験を重ねること、“こころ”と“からだ”で、まるごと音楽に向き合うことで、
音楽のさまざまな表情やニュアンスを聴きわける耳が育まれます。 ※8
ピアノも昔から根強い人気の習い事の1つです。聴覚が発達するこの時期に音楽とたくさん触れ合うことによって、聴く力や音感が育まれます。楽器を演奏できるようになったり、楽譜が読めるようになったりするだけでなく、集中力が養われたり、想像力が豊かになったり、これからの人生を彩ってくれるのではないでしょうか。
筆者の娘は音楽教室でピアノを習っていますが、最初は全く指が動かなかったのが、練習を重ねるうちに両手で1曲、また1曲と、どんどんひける曲が増えていきました。最初は悔しさで涙を流しながらひいていた娘が、今では誇らしげに季節の歌をひく姿に親としては感動を覚えました。
練習をすることで、悔しい気持ちや達成感を味わうことができるのも、この習い事の良い点だと感じます。
体操


体操は水泳と同じく全身運動で、なおかつ柔軟性も養えるところが魅力です。 ※9
体操は体のいろいろな部分を動かすので、全体的な運動能力の向上が期待できます。身体能力はどのスポーツにも求められるものなので、養っておいて無駄なことではないでしょう。体が柔軟になることによってケガや病気もしにくくなるのも、うれしいポイントです。
筆者の娘の体操教室では、跳び箱、鉄棒、マット運動など多岐にわたる運動をしています。器具や広いマットを使った運動は家ではなかなかできないので、楽しみながら取り組んでいます。また、他の同世代の子と一緒にやることによって、向上心も生まれ、良い刺激を受けながら通っています。
学習塾
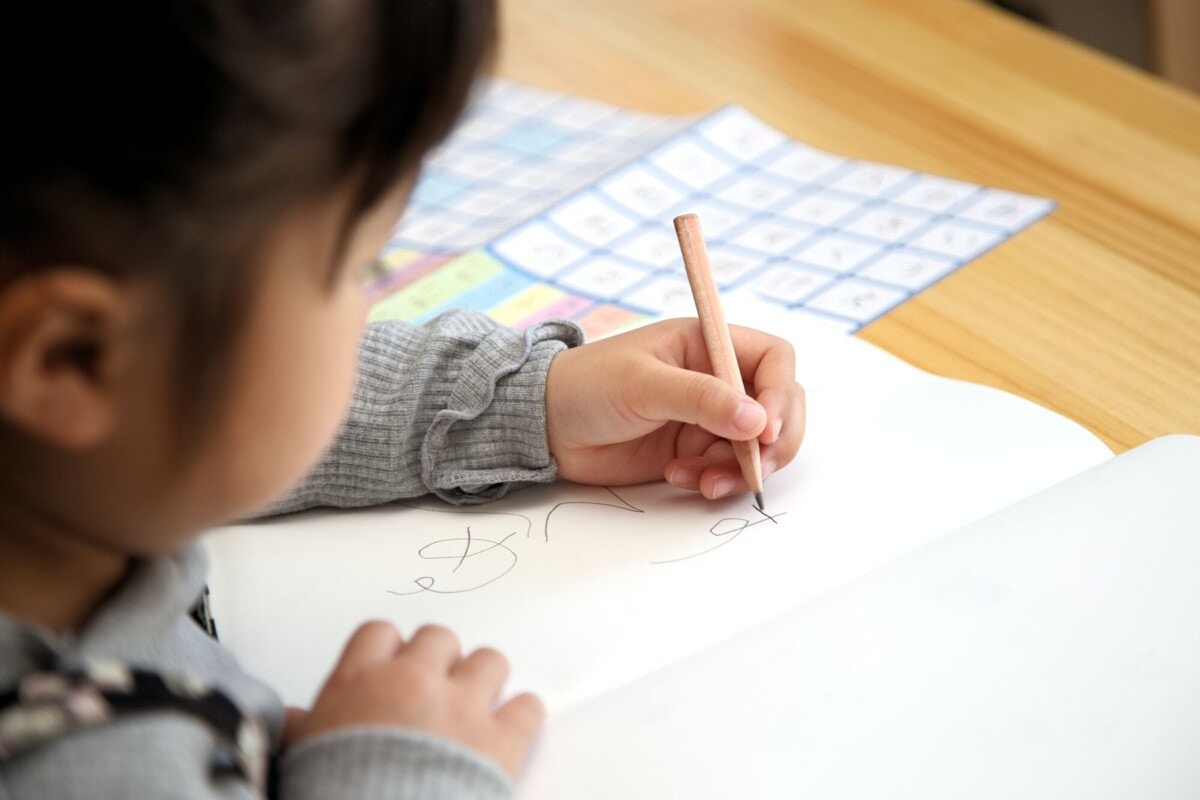

学習塾では早い段階から勉強する姿勢を身につけさせられますし、算数や国語といった小学校の中心的なカリキュラムを予習できるのも大きなメリットです。 ※10
算数や国語といった学習塾も幼稚園児に人気の習い事です。小学校で学ぶひらがなや、数字を幼児のころから学ぶことによって小学校で戸惑うことなく授業に参加することができます。また、座って勉強をするという習慣を早い段階でつけることにより、学校という環境に早く慣れることができるのではないでしょうか。
習い事はどれくらいの時間と頻度がいいの?
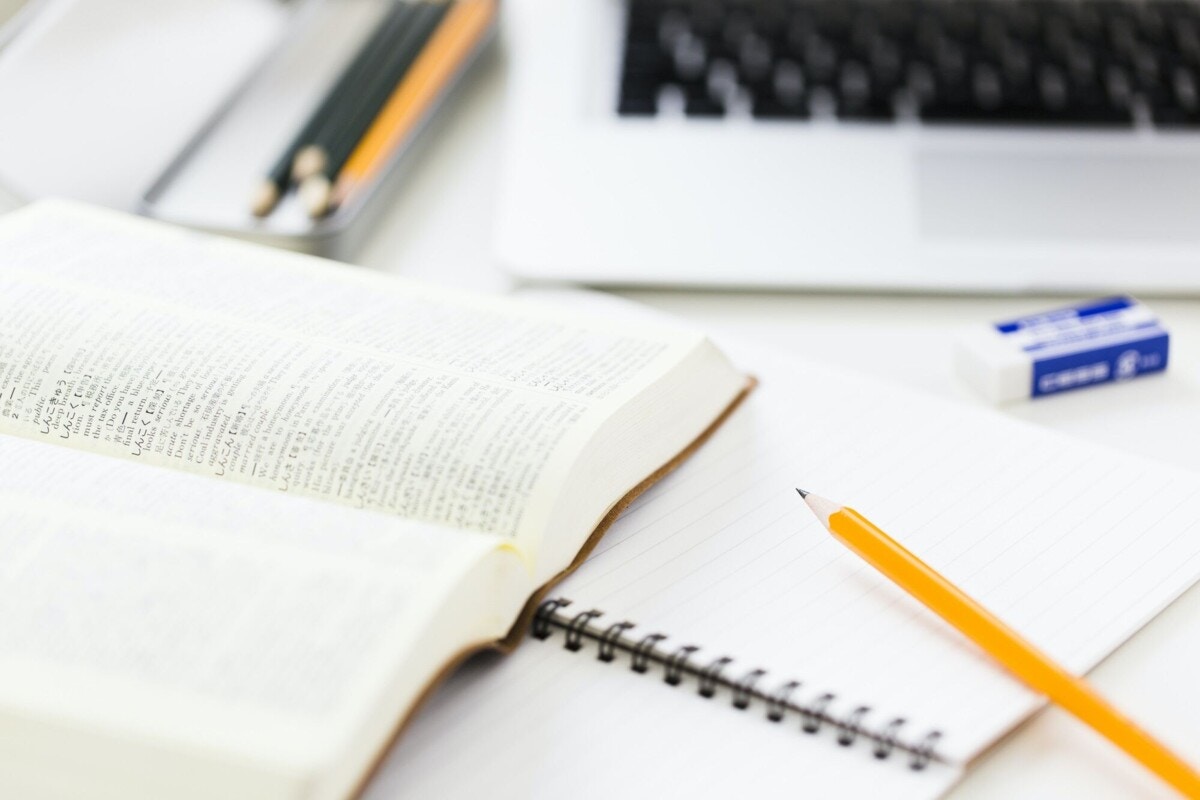

習い事はやればやるだけ効果があるのか。それとも1つだけをじっくりやるほうが良いのか。習い事の時間や頻度はどれくらいが良いのでしょうか。
たくさん習い事をやるメリットとデメリットを紹介します。
習い事をたくさんすることのメリット


1回の習い事が長くなるほど、または1週間の頻度が多くなるほど、その分体力や集中力がつきます。また、交友関係が広がり、友達もたくさんできるのではないでしょうか。また、習い事にかける時間が長い分、その能力がどんどん伸びていくメリットもあります。
習い事が多すぎるとデメリットも…


親としては、いろいろな習い事をさせて子どもに多くの経験をさせたいと思う気持ちもあるかもしれませんが、習い事をたくさんやることにはデメリットもあります。
「子どもは遊びが仕事」という言葉を聞いたことがないでしょうか。遊びは子どもにとって必要なものであり、それを通じて多くのことを学びとるのです。しかし、習い事を始めると、その分だけ友達と遊ぶ機会が減ってしまいます。それどころか、家族と過ごす時間まで削られる場合もあるでしょう。習い事のかけもちをして、家にいる時間が極端に短くなれば、子どもは睡眠不足に陥ることもありえます。また、親は送迎などの面で関わるのが一般的であり、多忙でもその時間を確保しなければなりません。このように親子ともに時間的なリスクがあるため、やみくもに習わせるのではなく、遊びとのバランスなどを意識して決めることが重要です。 ※11
習い事を増やすと、その分子どもが家で過ごす時間や自由に過ごす時間が減っていきます。本当は友達と遊びたかったり、家で好きな遊びをしたかったりという気持ちがあるのに、習い事で忙しいとその気持ちを満たすことができません。そして習い事が嫌なものという意識に変わっていくかもしれません。
また、親からの期待を感じ取り、それをプレッシャーに感じてしまうこともあります。子どもの気持ちを見ながら習い事の頻度や回数も考えていきたいですね。
週に2種類くらいで家族の時間も大切に


子どもの体力や経済面から習い事の頻度や回数について考えると、週に2種類くらいの習い事をさせている家庭が多いようです。週に2種類程度なら、十分家族だんらんを過ごす時間がとれますし、習い事以外のことにも時間を割くことができます。 ※12
子どもにとっては習い事は体力的にも精神的にも簡単にこなせるものではありません。子どもが知らず知らずのうちにつらくならないよう、家族の時間や子どもの遊ぶ時間を削り過ぎないよう、気を付けなければいけません。
運動系と文化系から1つずつ選んだり、連日行くことにならないよう習い事の曜日を調整したりして、週に2種類程度なら親子ともにゆとりができてくるのではないでしょうか。子どもの様子を見ながら増やしたり減らしたりしていき、無理のないスケジュールで習い事を選んでいきましょう。
幼稚園児の習い事の不安…いくらくらいかける? 習い事先への送迎は面倒?


習い事を始める際に心配なのが、それにかかる費用です。幼稚園児の習い事はどれくらいの費用をかけているのかをご紹介します。また、送迎も幼児の習い事には必要です。送迎についてもあわせてご紹介します。
習い事にはいくらくらいかけるものなの?


幼稚園児の習い事にかける費用は世帯年収や、年齢によっても異なります。
3歳4,300円、4歳(年
少)5,900円、5歳(年中)8,100円、6歳(年長)10,300円と、年齢が上がるにつれ、塾や習い
事にかける教育費も上がっていきます。 ※13
毎月の月謝の他にも、習い事によってはユニフォームや教材費、遠征費用などが必要になることもあるので、年間を通してみると想定よりも出費が多くなってしまうこともあります。習い事を始める際にチェックしておくと安心です。
習い事への送り迎えが大変?


習い事によっては送迎バスがある習い事もありますが、幼稚園児では利用ができないことがほとんどです。その場合、保護者の送迎が必要です。近場であれば苦にはならなくても、距離がある場合は電車やバスの交通費がかかったり、車で運転したりしなければいけません。
また親が共働きの場合は、どちらが送迎をするのか、仕事の都合をつけるのかをあらかじめ夫婦で話し合っておくことも大切です。土日しか休みがない場合は習い事によって家族でのんびり過ごす時間が減ってしまうので、家庭内でバランスを考えながら決めていきたいですね。
習い事は1回限りではなく、毎週や隔週であるので、いくら内容が子どもに合っていても送迎自体が親の大きな負担にならないように選ぶことも大切です。
子どもや家庭に合った習い事を見つけてみよう


幼稚園児から始めることができる習い事はたくさんあります。好奇心が強く、多くのことを吸収できるこの時期に子どもに合った習い事を見つけてみてはいかがでしょうか。まだ何がやりたいのかが明確ではない場合は、資料請求や体験を利用して焦らず子どものやりたいことや、伸ばしたい能力を探してみましょう。
幼稚園児の習い事には送迎や宿題のチェック、練習に付き合うなど、親の協力が不可欠です。子どもが楽しく続けられるのはもちろんのこと、親も無理せずに続けられるそれぞれの家庭に合った習い事が見つかると良いですね。