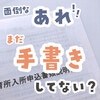©️itsumama_home
©️itsumama_home
小学生ママイチオシの育児アイテム
今回、ご紹介するのは、「時間」の感覚を覚えるのに最適なグッズ。その名も「時っ感タイマー」。小学生の子どもがいる保育士ママイチオシのアイテムです。
時間を忘れてゲームやテレビに没頭してしまった時や、歯磨きや宿題の時間の目安などにも活躍しています。今回は、このタイマーをどのように使用しているかをご紹介します。
PR

時間の感覚を身につけるのに最適!
 ©️itsumama_home
©️itsumama_home
わが家で大活躍の「時っ感タイマー」。タイマーなので「ピーピー」と知らせてくれるのですが、音の長さを「3秒」と「60秒」で選べます。
わが家では、3秒で十分なので、60秒は使ったことがありません。また、音量も選べるので、テレビに集中してしまっている時は、音量を「大」にしておくこともありましたが、生活の中で使用するときは「小」で十分です。
 ©️itsumama_home
©️itsumama_home
 ©️itsumama_home
©️itsumama_home
子どもは「ちょっと」や「少し」というような、「時間の感覚」がなかなか分かりません。
大人の都合で待たせている時や、おもちゃの貸し借りの時にタイマーを使うのですが、つまみを回すと、残り時間が緑色になります。少しずつ緑の部分が減っていくので、「みどりちゃんがいなくなったら、ママ洗濯物終えて行くね」などと声をかけておくと、ママの言ってる「ちょっと」はこれくらい。と分かるのです。
 ©️itsumama_home
©️itsumama_home
初めは母管理だったので、1つでよかったのですが、次第に自分で使えるようになり、兄弟で同じタイミングで使うこともあります。そのため、2台購入しました。
小学生になり、自分の時間を自分で管理するようになり、やはり1人1台あってよかったと思っています。
最初が肝心!使う時のポイント
 ©️itsumama_home
©️itsumama_home
「おもちゃではない」ということを認識させるのがポイント!あくまでも、「時計の仲間」であり、時間を知らせてくれるものとして、子どもたちに伝えましょう。
 ©️itsumama_home
©️itsumama_home
ここは要注意かなと思っているところです。このタイマーのいいところは、時間を可視化してくれること。それにより、「ちょっと」などのあいまいな言葉による、感覚の違いが解消され、親子のイライラも軽減されます。
ですが、何でもかんでもタイマーを使ってしまうと、時間の制限が増えてしまって、タイマー自体がキライになってしまう可能性も。使いすぎには気をつけましょう。
 ©️itsumama_home
©️itsumama_home
テレビやゲームに関しては、目安として使っています。例えば「テレビは30分」と決めていても、話が途中で途切れてしまっては、内容や結末が分からずに終わってしまうことも…。それではかえってフラストレーションがたまってしまうこともありますよね。
ですから、30分のタイマーをかけておいて、「30分たったんだ」という感覚は持ってもらいつつ、「タイマーが鳴ったから、キリのよいところで終わりにしようね」と声をかけておくといいですよ。
もちろん100%というわけにはいきませんが、続けていくと時間の感覚が分かってきます。
子どもと一緒に時間を決めよう
最後に、大事なことをおしらせします。タイトルにもあるように、子どもと「一緒に」時間を決めることが、自立への近道です。
タイマーをセットする時には「ここまで」と指定して、お子さんにセットしてもらうことが大切です。そうすることで「自分でセットした時間」という感覚を持ってもらうと、切りかえもしやすいのです。
上手にタイマーを使って、大人も子どももイライラせず、自分の時間を有意義に使えるといいですね。