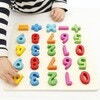年中から勉強を始めるメリットとは
年中のうちから勉強を始めると、小学校に上がってからのメリットがたくさんあります。まずはどんなメリットがあるのか確認してみましょう。
小学校の授業に余裕をもって臨める
小学校に上がるとクラス単位での授業が始まりますが、1年生の時点でも学習能力はそれぞれ異なり、授業の進み具合についていけないと成績も伸び悩んでしまう可能性もあります。
ひらがなや数字を覚えているだけでも、授業にゆとりを持って取り組むことができますし、理解度も早いので小学校での勉強を楽しいと感じられるようになっていくでしょう。
自宅学習の習慣が身に付く
「小学生になったから今日から家でも勉強!」と突然言われても、お子さんも戸惑ってしまいますよね。年中さんのうちから、少しずつ家で勉強する時間を取っておけば、小学生になっても自然と自宅学習する習慣ができているので、学校の宿題や予習復習にも抵抗なく取り組めるようになります。
新しい学習の吸収が早い
2020年からは小学校でも英語の授業が必須となり、プログラミングの教育も始まっています。いずれもこれからの国際化社会、IT社会には必須の能力になるでしょう。難しいことでも小学校に上がる前から少しずつでも学んでいけば、より吸収しやすくなるでしょう。
- 文部科学省「平成29・30年改訂学習指導要領のくわしい内容」(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1383986.htm#section4https://miraino-manabi.jp/,2021年2月10日最終閲覧)
年中の勉強におすすめのプリントや教材
年中からの勉強は自宅学習が主なものになりますが、パパ・ママ世代のころよりさらに進んだ内容になっていることもあり、教えるのも難しくなりましたよね。
そこで頼りになるのが、市販されているプリントや教材です。どんな教材がいいのか迷っている方のために、年中からの勉強におすすめのプリントやアプリを探してみました!
【ドリル】学研のワーク『もじ』『かず』『ちえ』
PR

学研ステイフルのワークは、年齢別に「もじ」「かず」「ちえ」の3分野で学べる教材です。
全ページフルカラーで、かわいいイラストや興味を引く内容になっています。教材としては理解するごとにステップアップしていくスタイルなので、お子さんのやる気も長続きするでしょう。毎日少しずつ楽しく学んで、小学校での授業に備えることができます。
【ドリル】4歳・5歳・6歳小学校の勉強ができる子になる問題集
PR

『4歳・5歳・6歳小学校の勉強ができる子になる問題集』は、絵本のような冒険の物語を読みながら楽しく学習できるドリルです。
小学校での勉強に役立つ数量や図形、言語、理科知識などがしっかり身に付き、遊びの延長のように積極的に取り組むお子さんも多いと好評!初めての自宅学習にもおすすめです。
【プリント】すくすくどんどん4~5歳
PR

すくすくどんどんプリント版は、「ことば、ずけい、かず・りょう、さぎょう」の4分野がバランスよく学べるプリントです。製本版もある商品ですが、コピーなどをしなくても手軽に少しずつ学習できるプリント版がおすすめ。まずはどんなものか試してみたい人にもぴったりの商品です。
【アプリ】dキッズ


月額409円(税込)で6,000以上のアプリ内コンテンツが使い放題のdキッズ。ひらがなやカタカナの書き方を覚える「指ドリル」や、パズルで遊びながら日本地図を覚えられる「ちずモン」など、アプリならではの操作で学習できるので、アプリで遊ぶことに慣れているお子さんなら抵抗なく始められます。
年中の子どもと勉強を進める時に押さえたいポイント


年中のお子さんに勉強させるときは、パパ・ママさんも教え方に悩むこともありますよね。どんなことに気を付けるといいのか、押さえておきたい事や意識したいポイントをチェックしてみてください。
なるべく毎日机に向かう習慣をつける
毎日少しずつでも勉強を続けるなら、習慣化することが重要なポイント。勉強するぞ!と意気込まなくても、毎日の習慣になれば自然と机に向かうようになります。
最初は勉強という形を取らなくても、一緒に絵本を読んだりお絵かきをしたりといった遊びから、決まった時間に机に向かってみてはいかがでしょうか。
子どもが飽きないよう工夫する
年中さんの学習は「基礎」が多いので、シンプルな計算や単調な書き取りなどが必要です。こうした基礎の学習は4歳くらいの年中さんだとすぐに飽きて「やりたくない」となってしまうことも。
子ども向けの教材には、絵本のようなカラフルで楽しいものや、音楽つきのDVD、ゲームのように勉強できるアプリなどさまざまなものがありますので、そういったものも利用しながら、お子さんが飽きずに続けられるよう工夫してみてください。
暮らしの中に学習を取り入れる
言葉を覚えることや簡単な計算をするには、ふだんの生活の中にもヒントが隠されています。
たとえば、おやつを使って数をかぞえてみたり、お店屋さんごっこをして「りんご3個でいくら?」と計算させてみたり、生活に欠かせない基礎的な学習を取り入れることができます。一緒に遊びながら学ぶことで、お子さんとのコミュニケーションを取ることもでき、「勉強は楽しいもの」という意識も高まります。
勉強を強制したり叱ったりするとNGな理由


家で勉強を教えていると、ついついイライラして叱ってしまったり、学習を強制したりしてしまいがち。
4歳くらいのお子さんに勉強させる時には、無理強いや叱るのはNGです。その理由と「叱らず進める方法」を一緒にご紹介します。
勉強に苦手意識を植え付けてしまう
勉強が嫌いな子どもも少なくありませんが、それは勉強が難しく大変だからという理由だけではなく、強制されたり叱られたりする経験によって苦手意識を持ってしまう場合もあります。
「なんでこんなことがわからないの?」「遊んでないで勉強しなさい!」などと強く言われて嫌な思いをすると、無意識に勉強そのものが嫌なものに感じてしまうことも。勉強しないことを叱るのではなく、少しでも取り組んだことを褒めるような、ポジティブなイメージを与えてあげてください。
自主的にやろうとする意欲を失う
勉強は必要なことだからと強制させようとすると、自主的にやろうとするのではなく、義務だからやらされているという受け身に感じてしまいがちです。
勉強の時間を習慣づけることも必要ですが、「親に言われるからやる」という意識ではやる気も起きにくいですし、効率がいいとは言えません。勉強することは子ども自身のためであることを理解させ、自分から勉強したいという意識に向けさせるよう、親子間での話し合いも必要かもしれません。
年中の勉強は親も一緒に楽しみながら!


成長していくにつれ、勉強はさらに難しくなっていきます。その入り口となる年中からの勉強は、勉強を楽しいと思えるよう、工夫を凝らした教材を用意したり、遊びも交えながら親も一緒に楽しめる方法を試してみてください。