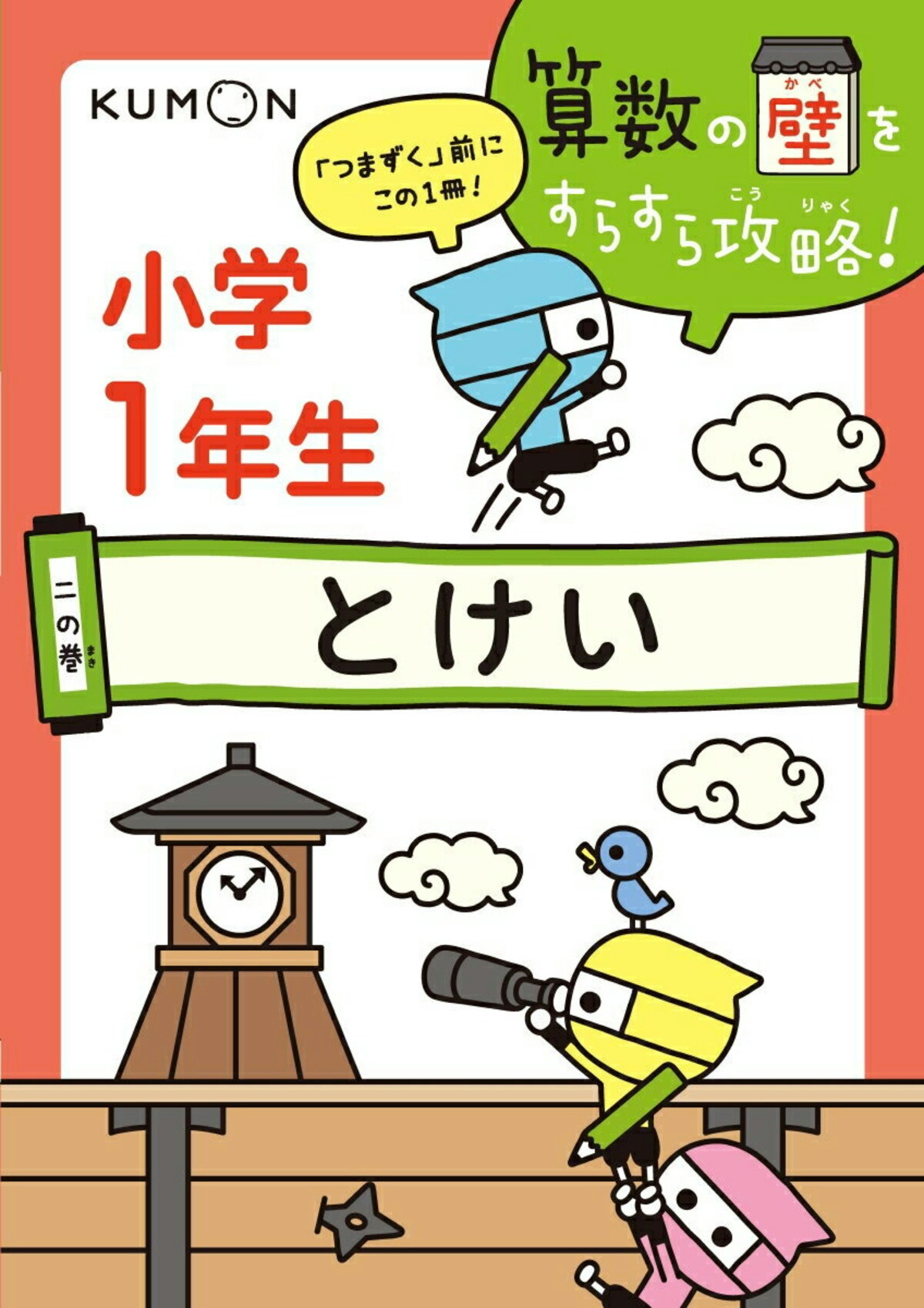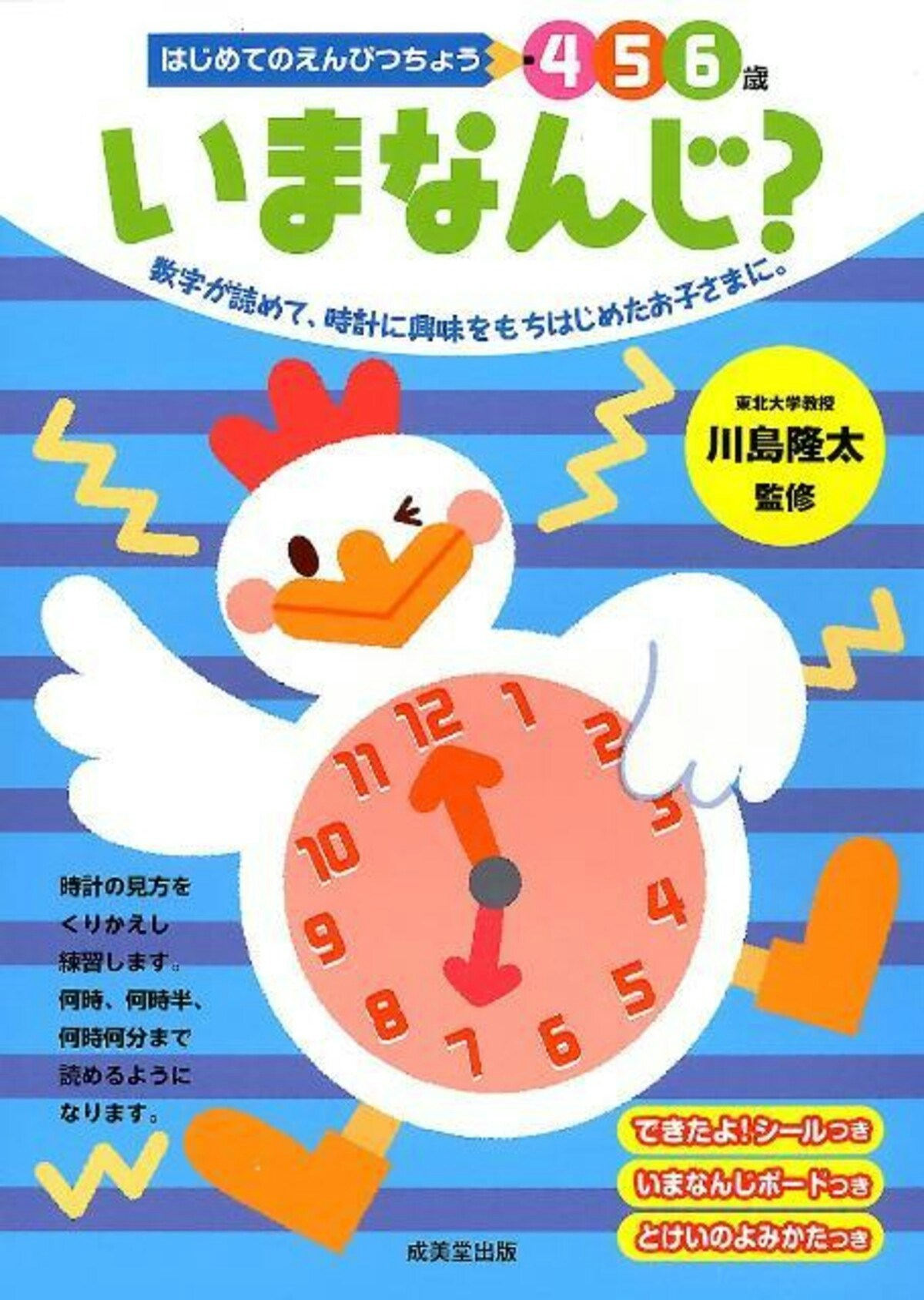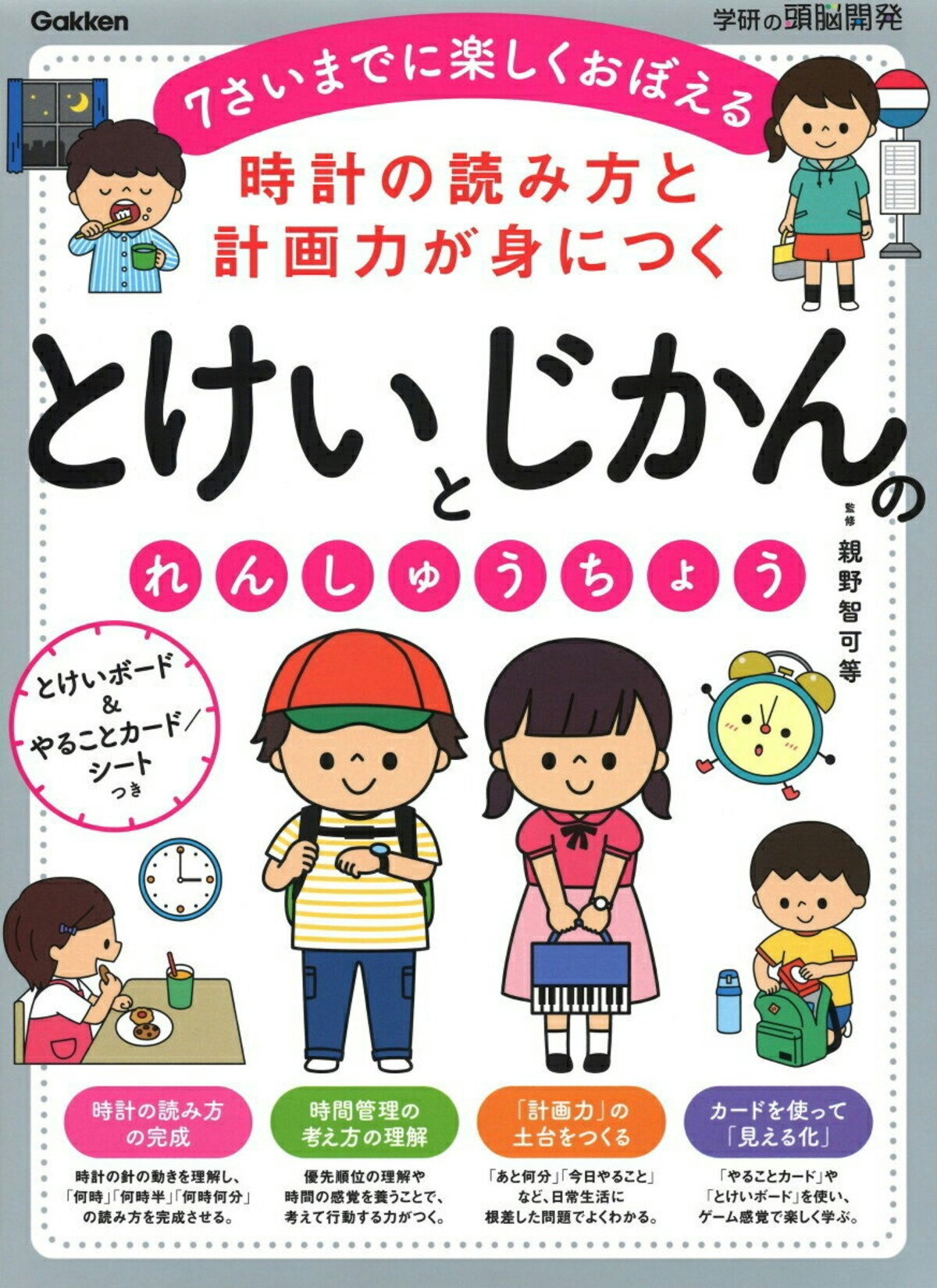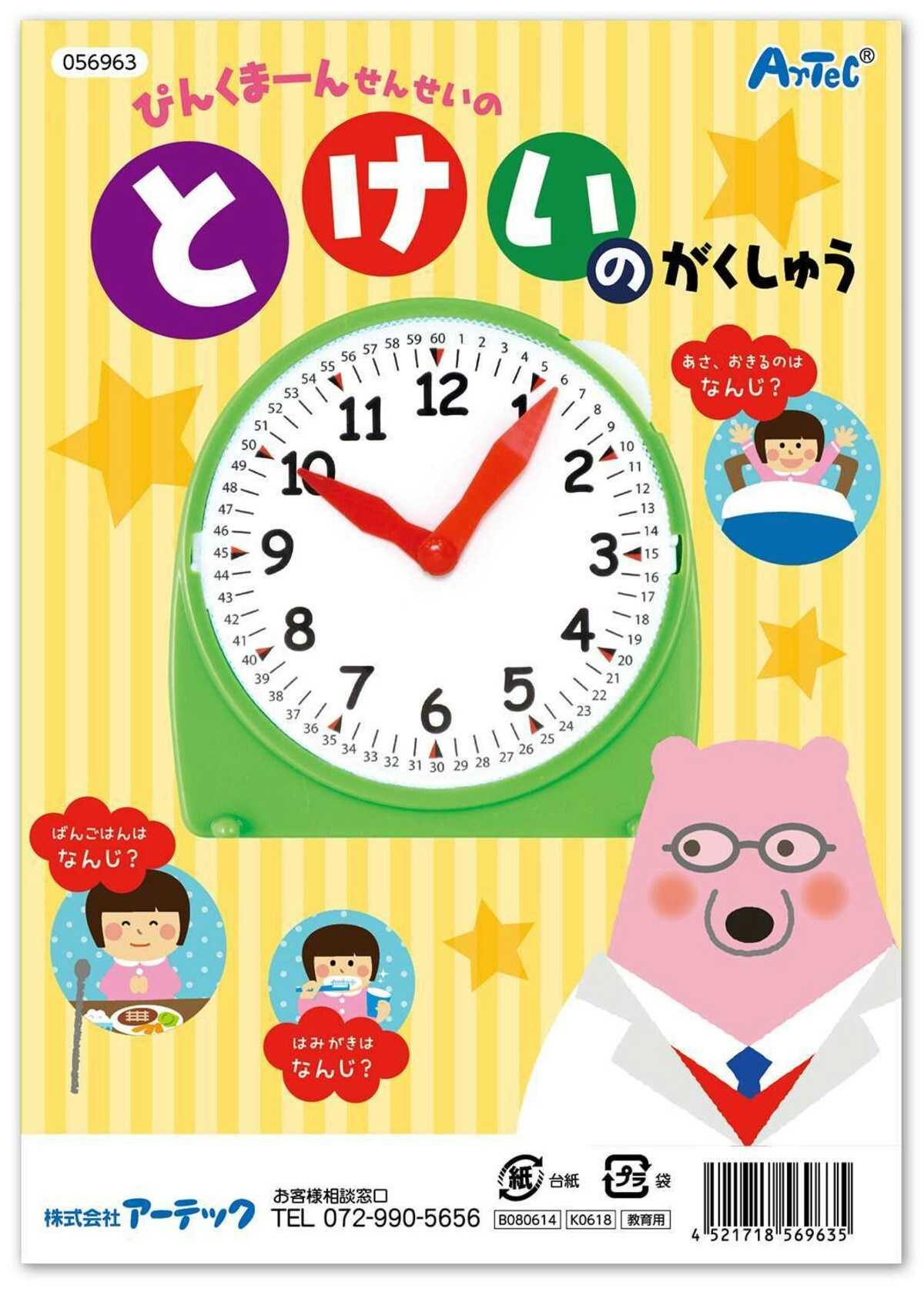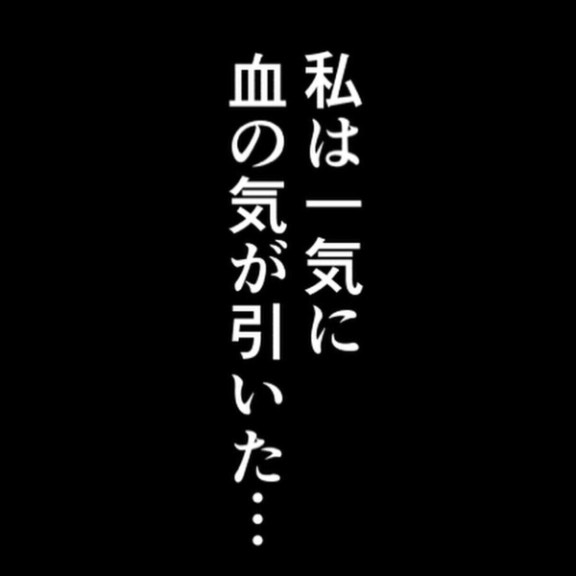時計の概念を理解できる年齢目安
まず、「時計」という概念を理解できるようになるのは何歳からなのでしょうか。一般的に数字を拾い読みできるようになるのは5歳ころから。
ですから、5歳ころから「時計の文字盤の数字」を読み始められる子は出てくるでしょう。ただ文字盤の数字が読めていることと、時刻を理解することは別です。
とはいえ、時計の数字が読めるようになったら、短針が指している数字を見て「何時だよ」と伝えることはできますね。
1年生になる前に時計の読み方を教えたいというパパママは、子どもが5歳前後になったころを目安として時計に親しんでいくと良いでしょう。
ただし、「1時間が60分である」「1日が24時間である」という感覚は、小学校1年生ではなく2年生の授業で教えられる内容。小学校1年生になる前の子どもが時計を読めなくても、時刻の概念が理解できなくても大きな問題ではないのであまり厳しく教えなくても大丈夫ですよ。
- 文部科学省「【算数編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説」(https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387017_004.pdf,2022年6月8日最終閲覧)
- ユニヴァーサル雙葉学園「子どもの特性」(https://www.ans.co.jp/k/universalfutaba/cgi-bin/topics3/upl/17-1.pdf,2022年6月8日最終閲覧)
小学1年生までに時計の読み方を教える方法


時刻の概念を理解できるのは小学校に入ってからで十分ですが、小学校1年生までに数字を見て短針の指している時間が言えると、小学校に入学するとき生活の役に立ちますね。それでは、小さな子どもに時計の読み方を教える方法についてステップごとに見ていきましょう。
STEP1:短針と数字の関係性を教える
小学校1年生までに時計の読み方を教えるには、まずは短針と数字の関係性から始めましょう。特に難しく考える必要はなく、「短い針が5のところにきたらご飯を食べようね」など、普段の生活の中で「短い針」を意識させるだけで大丈夫です。
よく見える場所に1分単位で刻みの入った大きめのアナログ時計を飾って、常に子どもの目につくようにするのがおすすめです。
STEP2:長針の00分と30分を教える
短針の読み方に慣れてきたら、次は長針の「00分」と「30分」を教えるステップです。
短針の読み方を教えたときと同じように、「短い針が5で長い針が12のところにきたら5時ちょうどだから、5時ちょうどになったらご飯を食べ始めようね」という風に、生活の中で「○時ちょうど」を覚えられるように声がけをしていきましょう。
ちょうどの時間を覚えられたら、同じように「30分」を子どもに意識させるようにします。7時ちょうどにお風呂に入りはじめて7時半に上がるようにするなど、30分間の行動をしながら教えると「30分」という時間の概念も理解しやすいかもしれません。
STEP3:さらに細かな長針の読み方を教える
「00分」と「30分」がわかるようになったら、さらに細かな長針の読み方を教えていきましょう。ただ1分単位で教えようとすると難しいので、まずは5分単位で教えていくとスムーズです。
「長い針が1のところにきたら5分だから、今から5分で準備をしようね」
「長い針が2のところにきたら10分だよ。10分になったら出かけようか」
と、アナログ時計の数字と「5分間」関連付けるような声がけをしていきます。ただし細かな長針の読み方は、子どもにとってはこれまでのステップよりも難しいこと。繰り返し声かけをして、少しずつ慣れさせていくことが大切です。
STEP4:1分単位で長針の読み方を教える
5分単位で長針の読み方がわかるようになったら、いよいよ1分単位の読み方を教える最終ステップです。1分単位の刻みを指差しながら、子どもと一緒に1~60まで数えるところから始めてください。
60分まで数えられるようになったら、「5時3分」に時計をあわせて何時何分かクイズのように質問してみましょう。子どもが楽しみながら学ぶためのコツは、遊び感覚で教えること。時計の読み方もクイズにすれば子どもも楽しく、きっとどんどん吸収してくれるはずですよ。
また、1年生の時計の問題をプリントとして印刷して、子どもに解かせるのもおすすめの勉強法。1年生の時計の問題は無料のプリントサイトなどからダウンロードできるので、おうちで手軽に学習ができますよ。
- NHK「本当は何時何分?~時計の読み方のポイントを考えよう~」(https://www.nhk.or.jp/school/aw/sukurepo/201802240186/,2022年6月9日最終閲覧)
時計の読み方に関する先輩ママの体験談


「小学校1年生になるまでに時計の読み方を教えたい」という思いは多くのママが抱くもの。そこでここからは、ママリに寄せられた先輩ママの体験談から、子どもに時計の読み方を教えた経験についてピックアップして紹介します。
子どもは関心のあることならすぐに覚えてくれますよね。4~5歳ごろに時計を読めるようになった子どもたちは、やはり時計に関心を向けていたことで自分から覚えた…というケースが多かったようです。
ただし、子どもに関心がなくても学習グッズの効果でスムーズに覚えられたという子どもも…。
小学校1年生になる前に時計の読み方を教えるなら、知育時計があると早く覚えられるようです。かなり手ごろな価格で販売されているものも多いので、時計の読み方を教えようと思ったらまずは知育時計を準備すると良さそうですね。
時計の読み方を教えるときにおすすめの知育時計


先輩ママも使っていた知育時計。1年生になる前に時計の読み方を教えるなら、時計の問題を解くより実際に知育時計を使う方が楽しく覚えられるでしょう。1年生までに時計の読み方を教えるときは、ぜひ次のような知育時計を使ってみてくださいね。
【VIKMARI】知育時計
PR

カラフルで子ども部屋にピッタリの知育時計です。小さく1分単位の読み方が書かれているだけでなく、24時間の読みにも対応しているので、小学校1年生になった後の時計学習にも使えそうなところがポイント。
秒針はスイープタイプになっていて「カチカチ」という音がせず、学習や睡眠の邪魔にもなりません。
【SEIKO】知育目覚まし時計
PR
![セイコー SEIKO 知育目覚まし時計 薄青パール KR887L [アナログ]](https://cdn-mamari.imgix.net/item/1200x0_61655136-bf84-4b04-8c5f-006d0a01047a.jpg.jpg?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
こちらもカラフルで楽しくなるようなデザインが魅力ですが、中央部分に「12じ」「1じ」と、子どもでもわかりやすいように1時間単位の読み方が書かれているので覚えやすいはず。
目覚まし時計なのでセットした時間になると音もなり、音と関連付けた読み方習得もできそうです。時計の読み方を覚えるためだけでなく、実用性にも優れた知育時計を求めている方におすすめします。
【ノア精密】知育時計 よ~める
PR

わかりやすさと丈夫さを重視されるママパパにおすすめなのが、こちらの知育時計。アクリル樹脂で作られているので、万が一子どもが落としてしまっても割れるリスクが少ない作りです。
色味・デザインともにとてもシンプルなので、純粋に時計の読み方を教えたいというときにピッタリです。付録として時計の読み方を教えるためのアドバイスがついてくるので、時計をなかなか覚えられない子どもに試してみてはいかがでしょうか。
【IFEND】壁掛け時計
シンプルデザインながら、針が鉛筆デザインになっていたり、ポップなカラーが用意されていたりと子どもが楽しく学習できる要素がふんだんに盛り込まれた知育時計です。
時計の目盛りには外側に「0~60」がわかるように数字が割り振られているので、秒単位の読み方も覚えられます。
イエローやブルーは子ども部屋にピッタリで、シンプルな白はリビングにかけてもインテリアを邪魔しません。おしゃれに知育時計を取り入れたいという方におすすめですよ。
【プリズム】クロキッズ 知育時計
PR

木製でおしゃれなのが特徴のクロキッズ知育時計。なんと直径60cmという大きさなので、嫌でも子どもの目につきます。
12~3は赤、3~6はオレンジ、6~9は水色…と、色によってその時間帯の雰囲気を表現しているので、時計の読み方が覚えられない子どもでも、小学校1年生になる前に感覚的に学べるのではないでしょうか。
カラフルさはインテリアを楽しくしてくれるでしょうから、子どもが大きくなってもそのまま使い続けやすいこともメリットですね。
時計の読み方を学習できるおすすめの教材
小学校1年生になる前の子どもに時計の読み方を教えるなら、知育時計とともに欠かせないのが教材です。小学校に入ってからの学習なら、視覚だけでなく書きながら覚えるのもおすすめの方法ですよ。
それでは子どもが時計の読み方を学習するのに、おすすめの教材について見ていきましょう。
【くもん出版】とけい(算数の壁をすらすら攻略)
くもんから販売されている、時計の読み方に特化したプリント問題集です。時計の読み方の基本から応用までを無理なく学び、算数力も養えるのが特徴です。
時計の読み方の学習と言えばアナログ時計を読むのが一般的ですが、この問題集ではデジタル時計についても触れています。時間を1日の生活と結びつけて覚えられる仕組みなので、「1日の時間」を子どもの実感として習得しやすくなっていますよ。
【成美堂出版】いまなんじ? 4 5 6歳 数字が読めて、時計に興味をもちはじめたお子さまに。
こちらのプリント問題集は、対象年齢が4歳からとなっているので、小学校1年生になる前の子どもでも無理なく取り組めるはずです。
フルカラーで描かれたかわいい動物のイラストとともに、数字をなぞるところから学習が始まり、さらに「長い針はどちらに動きますか?」などの基本的なことも学習できます。
付録には「できたよ!シール」のほかに、問題集の中で使える「とけいシール」もついてくるので楽しく学べそうですね。
【学研プラス】時計の読み方と計画力が身につくとけいとじかんのれんしゅうちょう 7さいまでに楽しくおぼえる
学研プラスから販売されている1年生になる前の子どもに向けた時計の問題集は、時計の読み方だけでなく、計画のたて方やタスク管理の方法まで教えてくれるので実生活にメリットが大きいことが魅力となります。
時計の読み方を覚えても、実際に時間通りに動くことは難しいもの。この問題集で時間管理の能力や計画力を身につければ、小学校生活はもちろん、家での生活も時間を意識しながら行えるようになるかもしれませんよ。
【アーテック】ぴんくまーん先生のとけいのがくしゅう
実際に時計を動かしながら学習するタイプの問題集です。時計の読み方を教えるページでは、朝の7時に起きて、7時5分に歯磨きをして…と、1日の生活に沿って学習できるので子どもにとって時間をイメージしやすいでしょう。
7時のところには「げんきにおはようとあいさつをしましょう。」などのアドバイスもついていて、時計の読み方とともに正しい生活習慣も覚えられますよ。
日常的な声かけで1年生になるまでに時計を習得!


小学校1年生になる前に時計の読み方を教えるには、日常的に時間に関する声かけを続け、子どもに「時間」を意識させることが効果的です。時計の読み方をクイズ形式にしたり、紹介したおすすめの知育時計を使ったりして楽しく、遊び感覚で学習させてあげてくださいね。
時計が読めるようになると、小学校に入学した後も時計を見て行動できるようになるはず。記事の内容を参考に、少しずつ教えていきましょう。