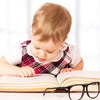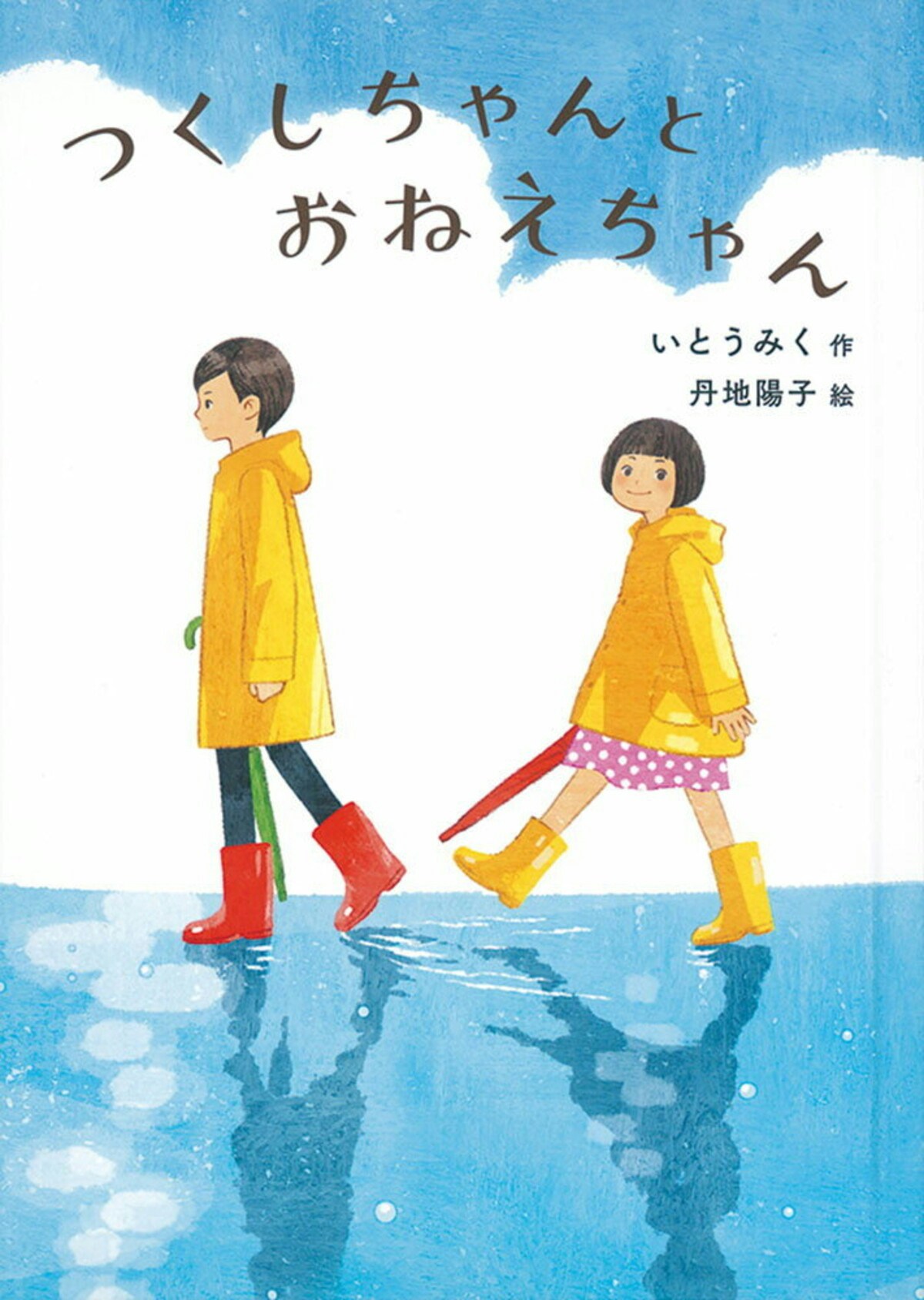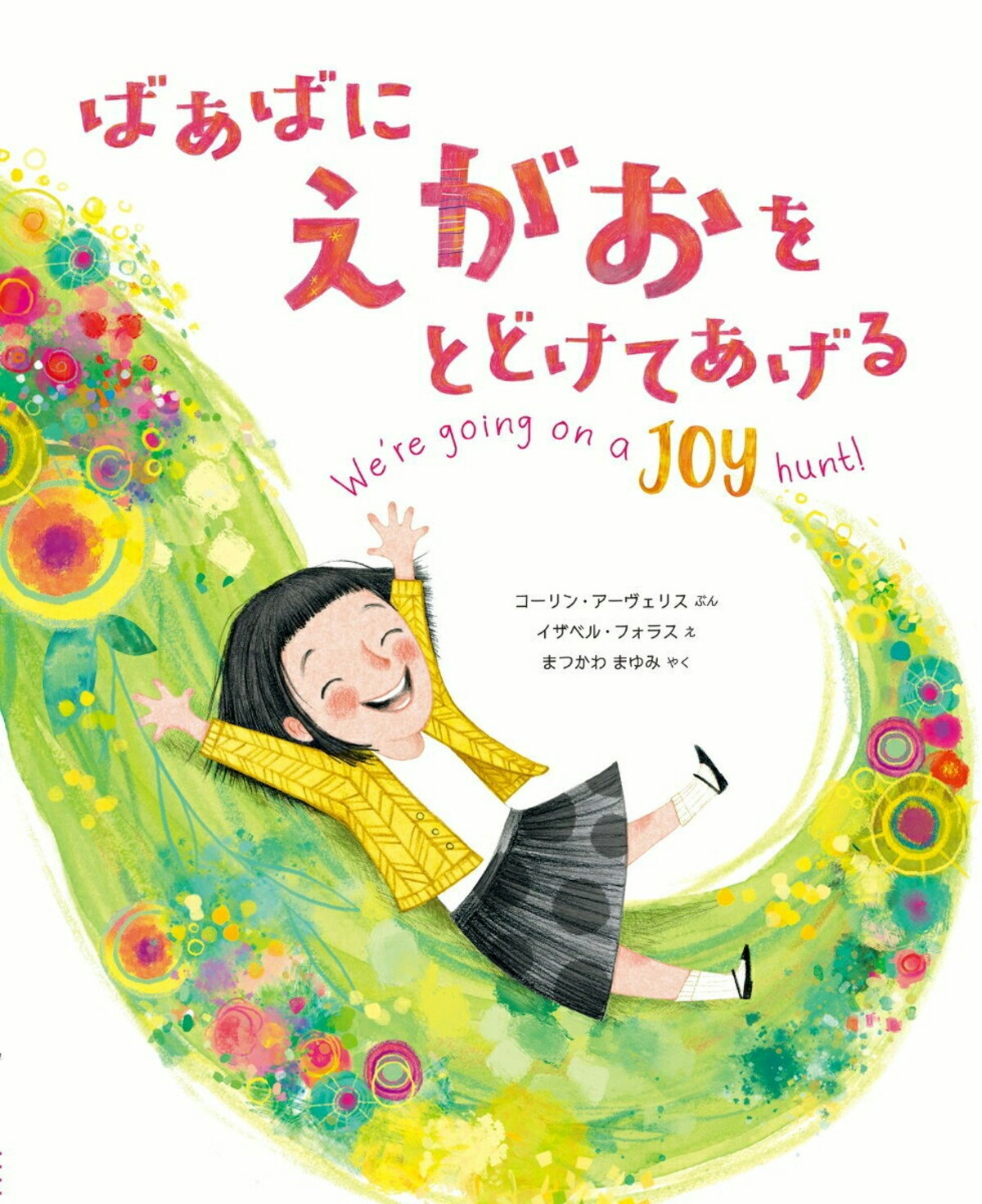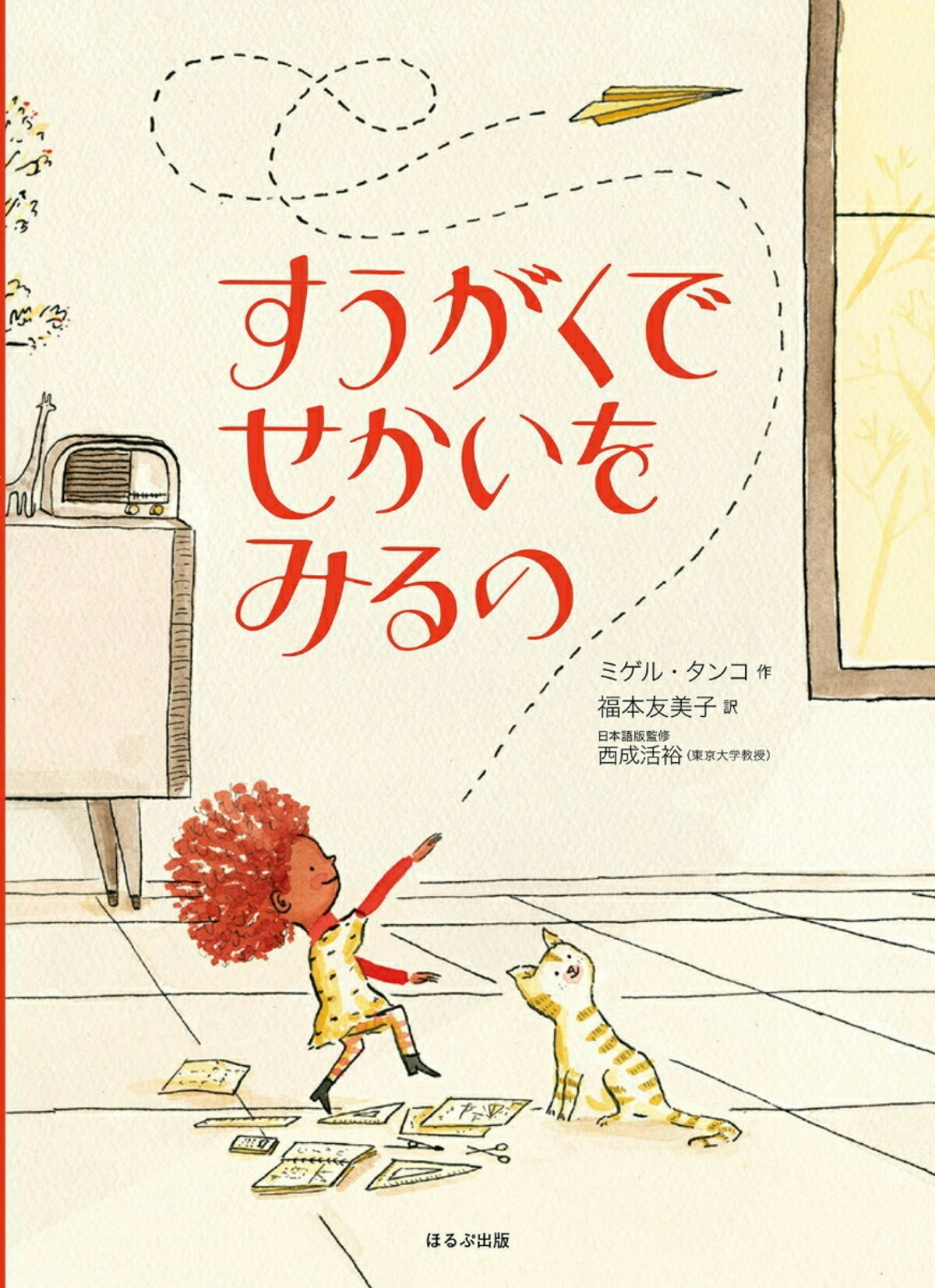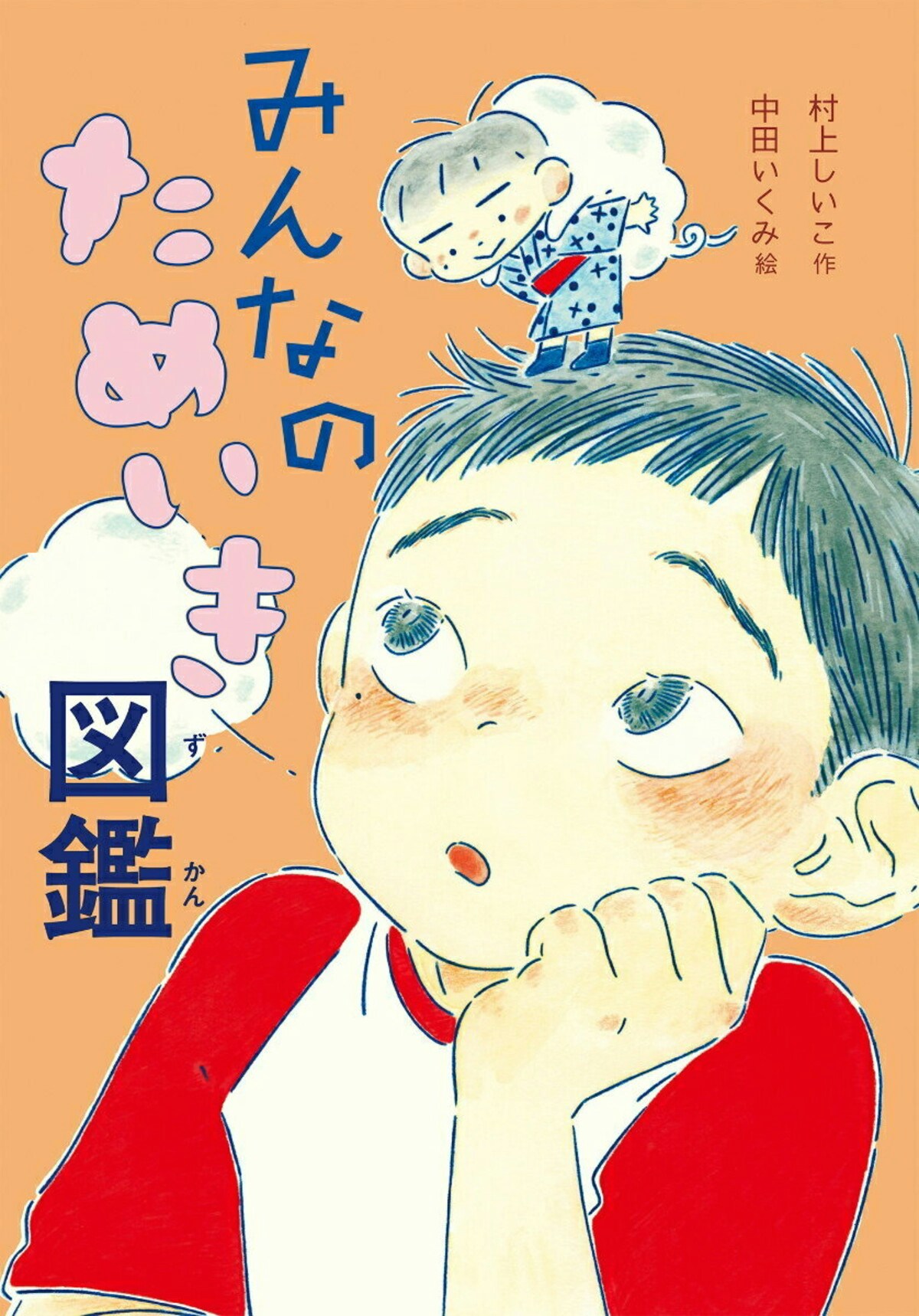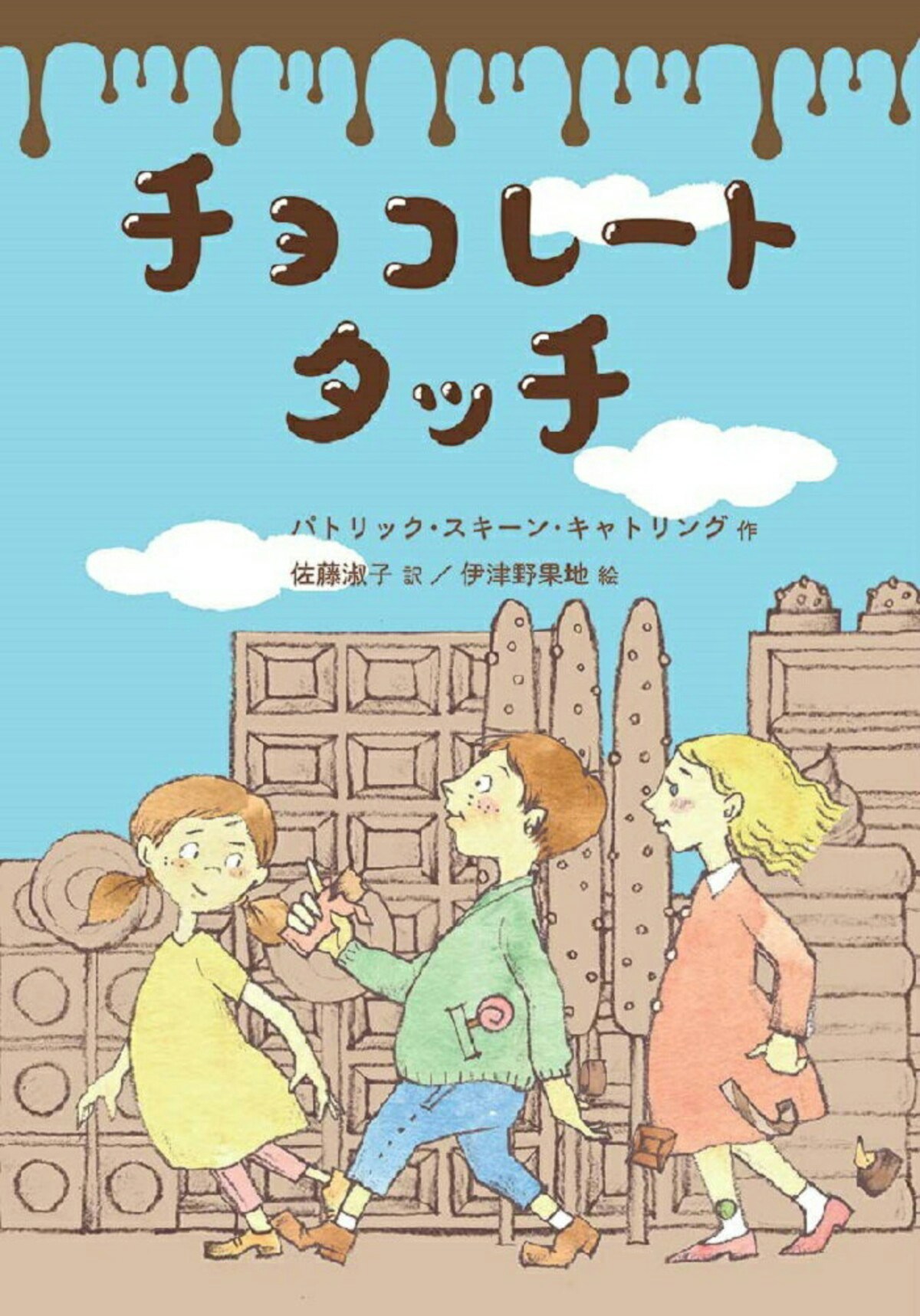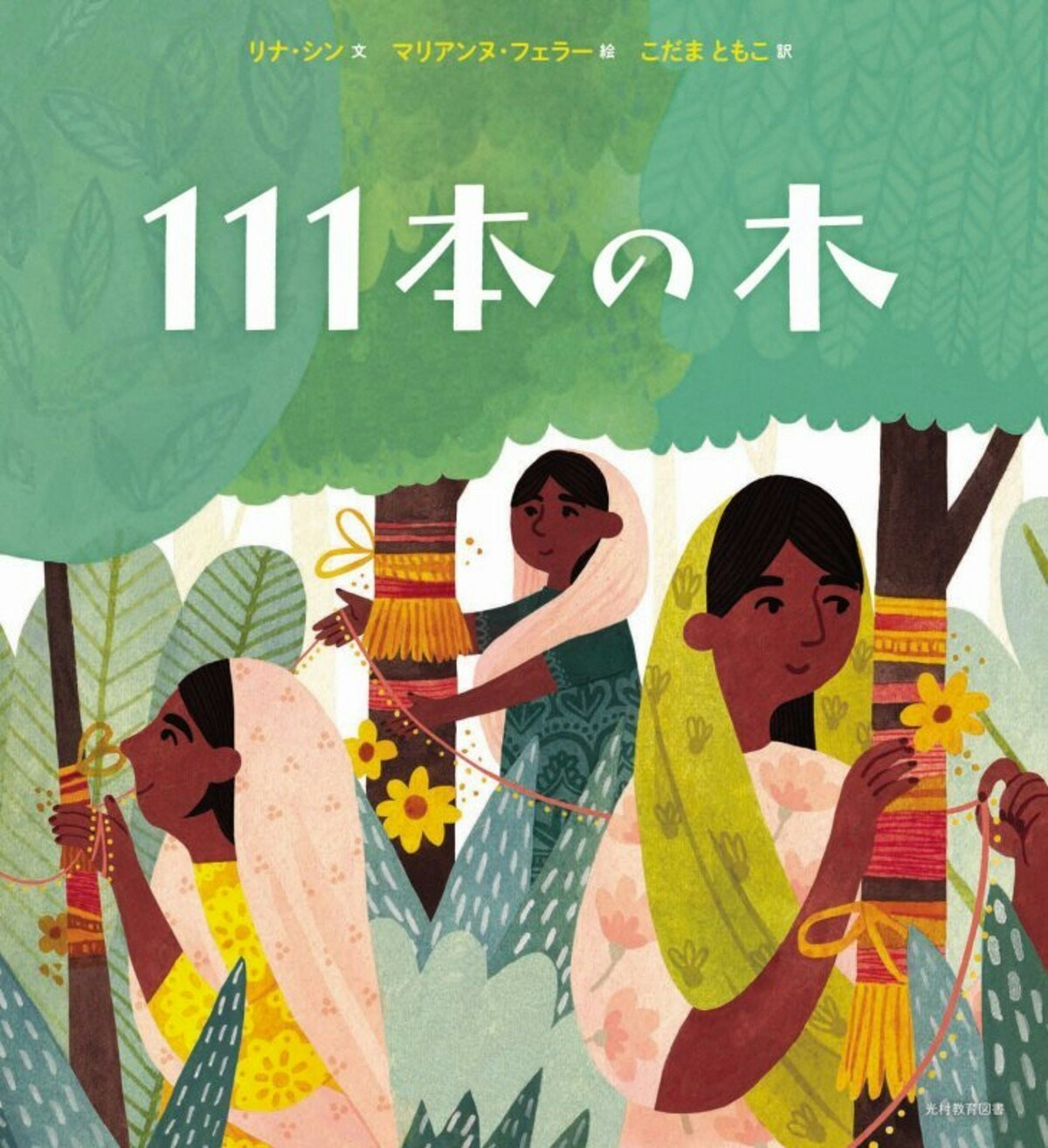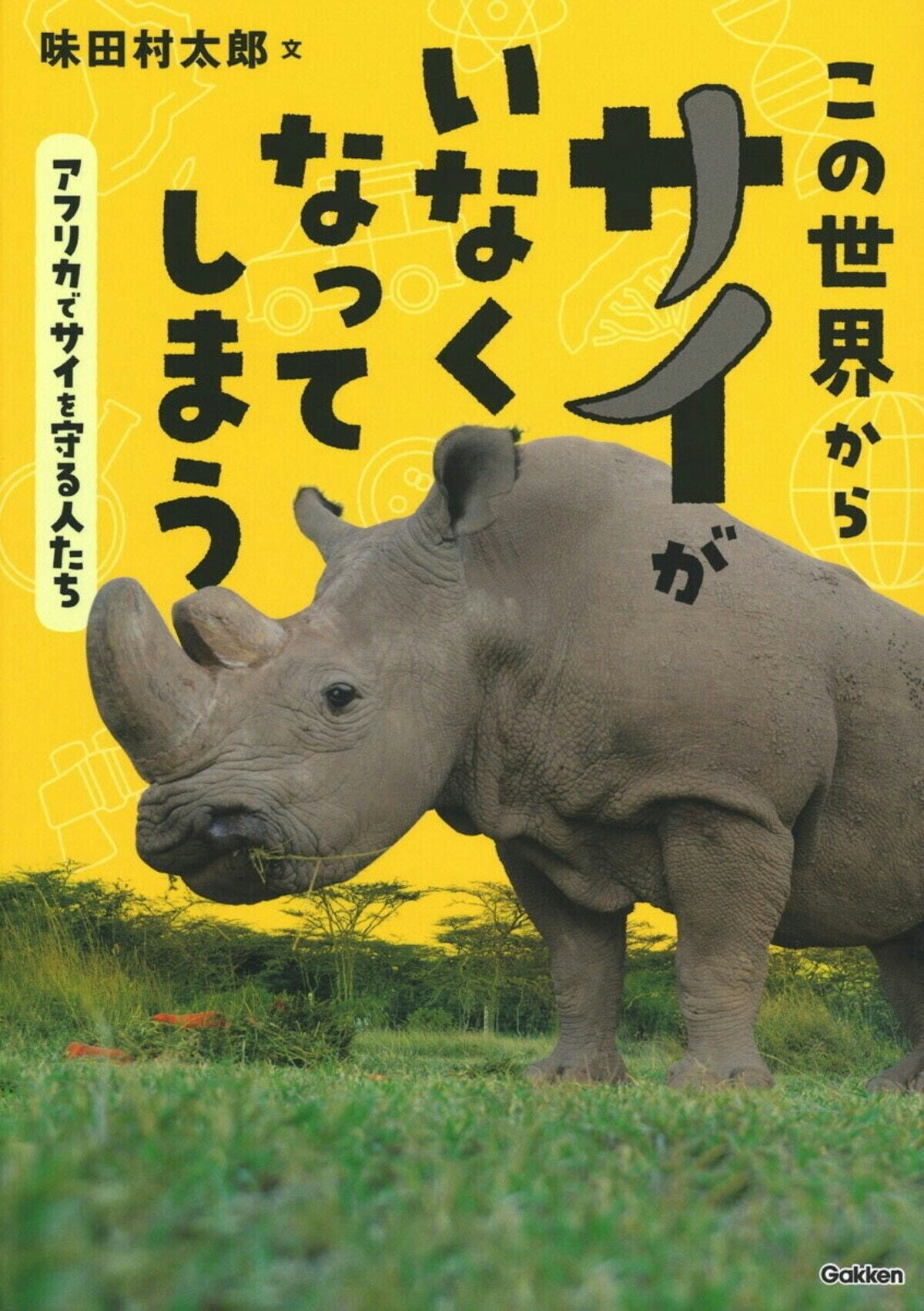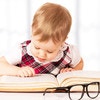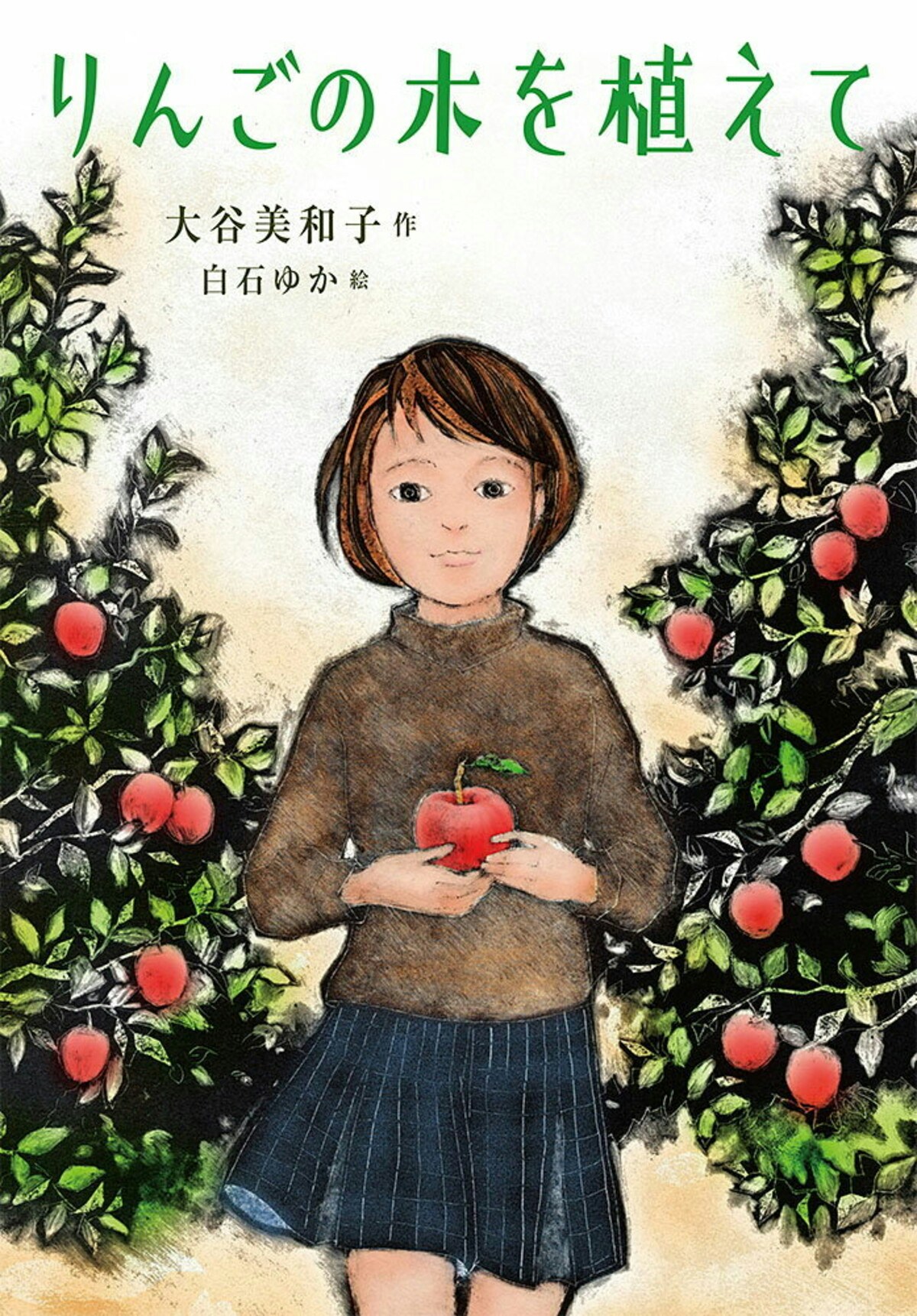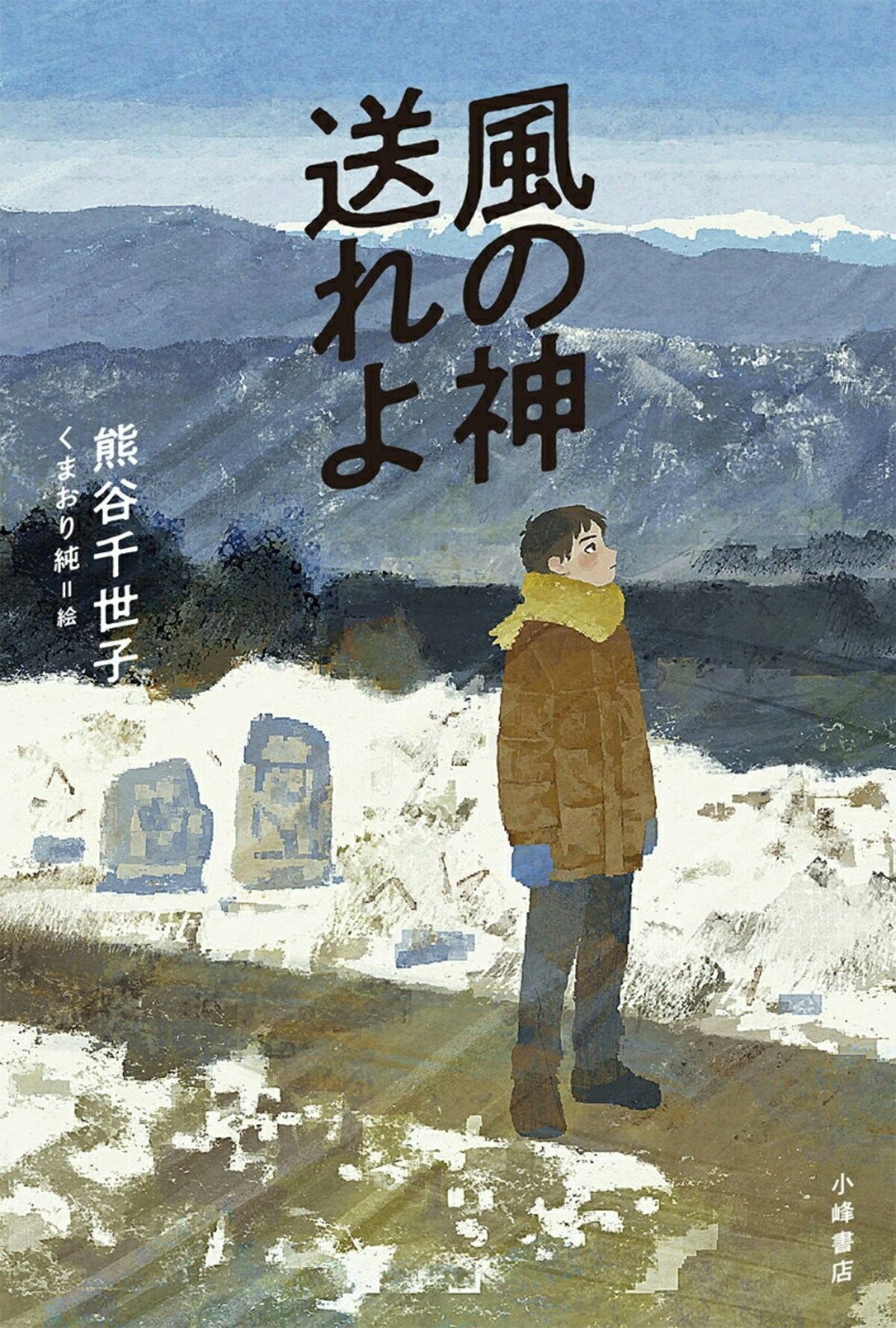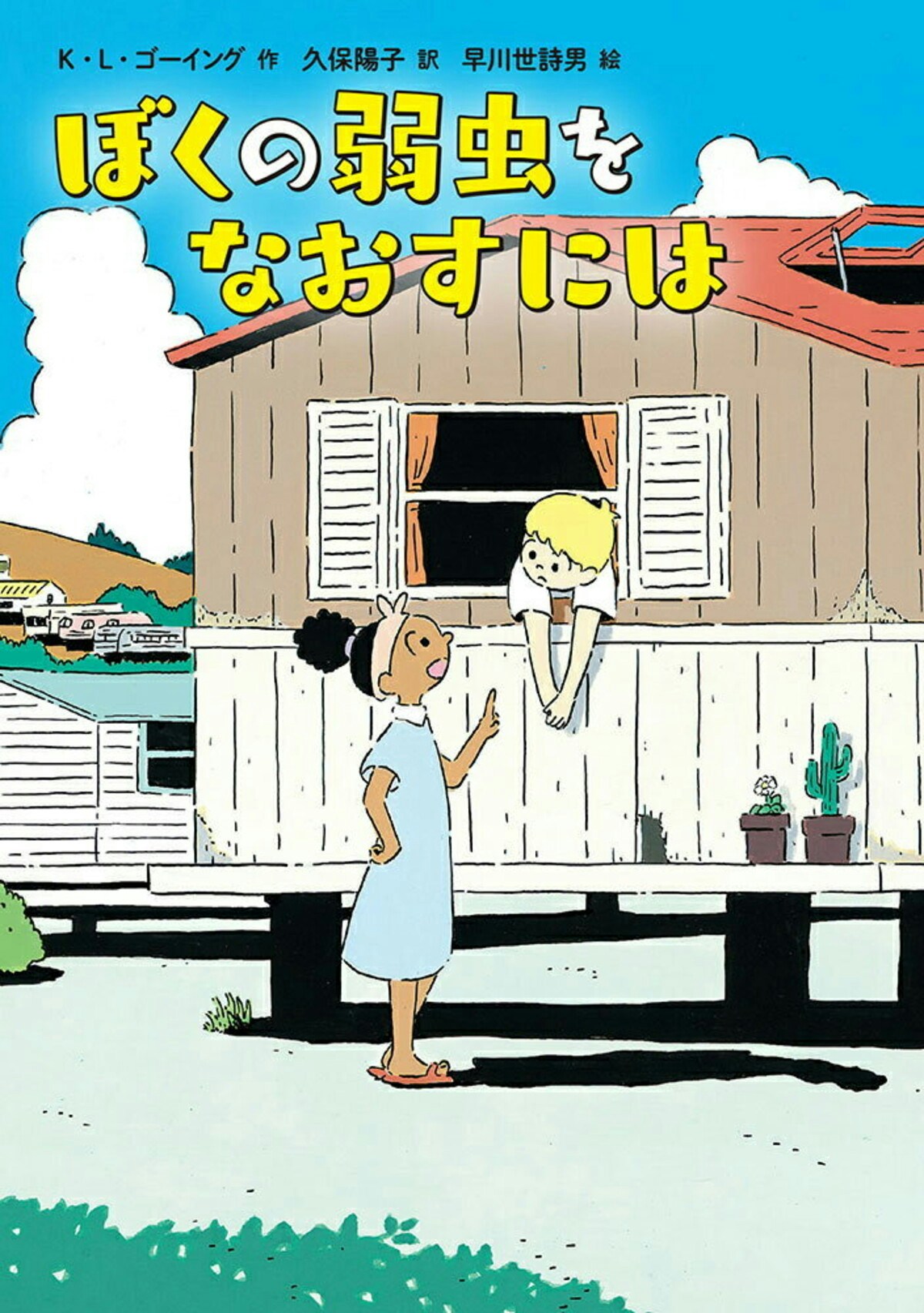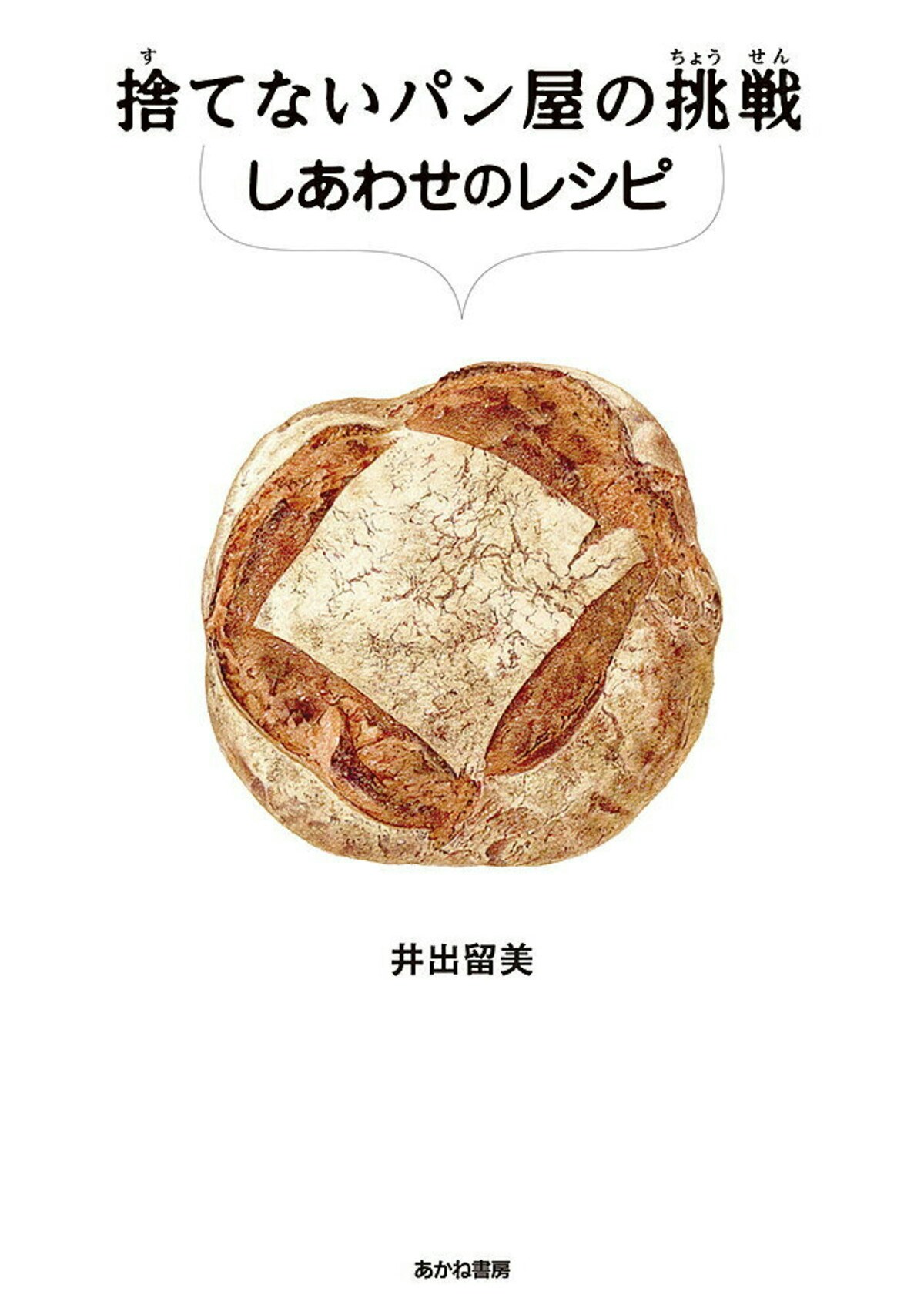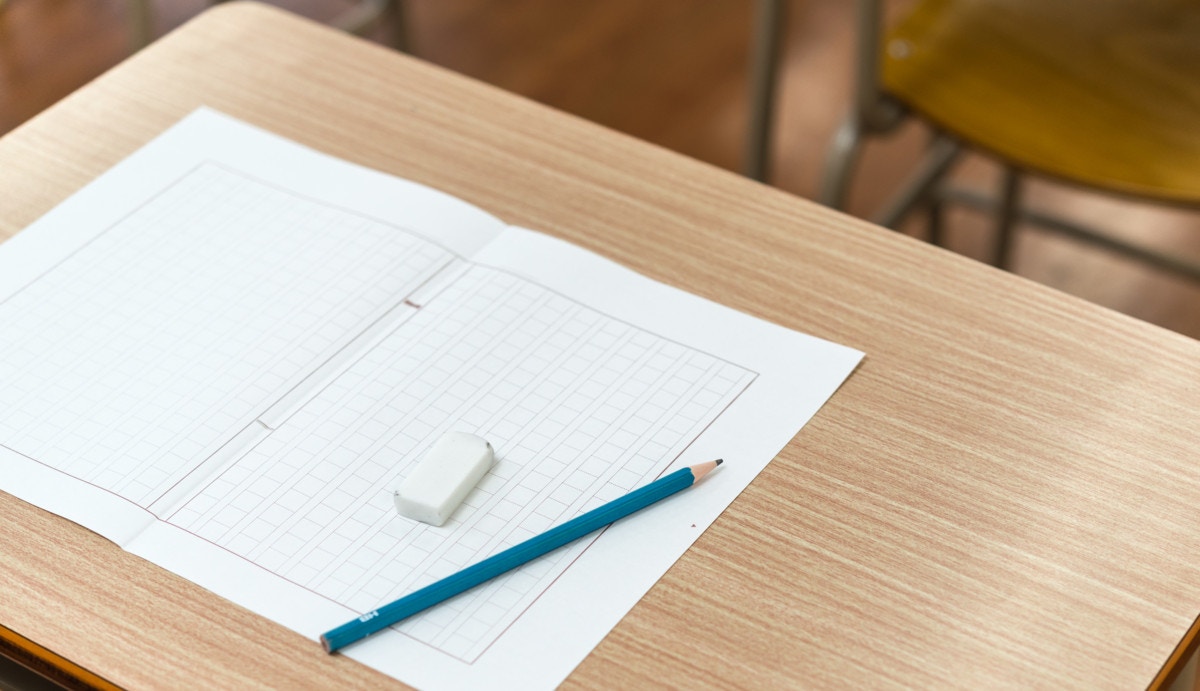

青少年読書感想文全国コンクールとは?
青少年読書感想文全国コンクールとは、サントリーホールディングス株式会社が主催する読書感想文コンクールです。
2022年で68回目を迎え、子供や若者が本に親しむ機会を作り、読書の慣習化が目的です。読書で抱いた思いを文章化することによって、考える力と正しい日本語で表現する力を養います。
応募対象者は、小学校、中学校、高校に在籍している生徒です。個人応募は対象外となっており、原則として学校を通しての応募のみの受け付けとなります。
対象図書は主催側が提示した課題図書もしくは、教科書や雑誌以外で自由に選んだ図書です。入賞した作品は毎日新聞や毎日小学生新聞、学校図書館、学校図書館速報版の紙上で発表されます。
さらに個人賞と学校賞が贈呈され、入賞作品は毎日新聞社が出版発行している「考える図書」に掲載されます。
文字数の決まりや書き方のルール
書き方のルールは原稿用紙に縦書きで記入します。文字数については学年によって異なり、以下のように規定されています。
- 小学校低学年の部(1、2年生):本文800字以内
- 小学校中学年の部(3、4年生):本文1,200字以内
- 小学校高学年の部(5、6年生):本文1,200字以内
句読点はそれぞれ1字として数えられ、改行のための空白も字数として数えますが、題名、学校名、氏名は字数に数えません。
応募は課題読書、自由読書それぞれに1人1編ずつ応募でき、応募は在籍校を通じて提出する必要があります。
審査方法
応募された作品は、まずそれぞれの学校内で審査され、市町村・地区審査会を経て、都道府県審査会で各部で優秀作品を選び、各部課題読書1編、自由読書1編が全国コンクールである中央審査会へ送られ、学校関係者や学識経験者によって審査されます。
- 全国学校図書館協議会「応募要項」(https://www.dokusyokansoubun.jp/youkou.html,2023年1月26日最終閲覧)
コンクールで入賞する作品の4つの構成例


読書感想文コンクールで入賞する作品にするための基本的な構成は、「本を決めたきっかけ・理由」「あらすじ」「本を読んだ感想」「読書後の変化」の4つです。
この4つの内容をバランスよく文章に盛り込むことで、高評価を得やすい読書感想文となりますが、これら4つの内容を順番に書いていく必要はありません。
むしろ評価の高い読書感想文は、内容が入り乱れている場合が多いでしょう。
1.本を決めたきっかけ・理由
本を決めたきっかけ・理由は、文章全体の約10%の文量が目安となります。本を決めたきっかけはほとんどの場合、課題図書だったからといった理由でしょう。
しかし、身近な単語がたくさんあった、親近感が湧いたなど、数冊ある課題図書の中から一冊を選んだきっかけは何かあるはずです。その理由を膨らませて文章とするのがいいでしょう。
2.あらすじ
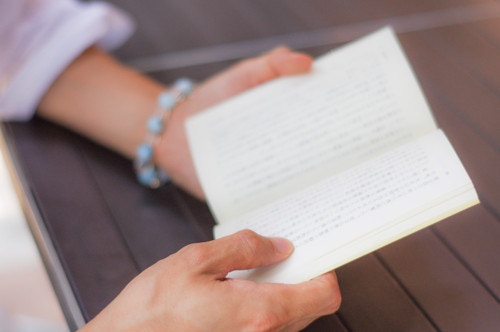

あらすじは文章全体の約20%の文量が目安です。本のあらすじは必ずしも書く必要はないといった意見もありますが、本を読んだことがない人にも伝わりやすい作品にするためにはある程度のあらすじは必要です。
ただし、あらすじは文字数を稼ぐ手段になってしまいやすいので、なるべく簡潔に短く納めるように意識しましょう。
3.本を読んだ感想
本を読んだ感想は文章全体の約30%の文量が目安です。感想となると、「面白かった」「すごいと思った」といった内容になってしまいがちですが、これだけでは不十分です。
どうして、どのように面白かったのか、感動したのかといった部分も必ず書くようにしましょう。
4.読書後の変化
読書後の変化は文章全体の約40%の文量が目安です。ここでは、本で読んだ感想を受けて、何を考え、学んだのか、そして自分自身がどのように変わったのか、という内容を書きましょう。
本を読んで学んだことや考えたことを、どのように文章化しているかということがとても重要であり、読書感想文の中で審査員が最も読みたい部分です。
しかしここは読書感想文の中でも最も難しい部分でもあり、上手く表現できる人は少ないようです。
金賞を狙う!書き出しテクニック


高評価を得やすい読書感想文の書き出し方は主に2つあり、本文引用の会話から入るパターンと、自分の感情から入るパターンです。
本文引用の会話から入るパターンの場合、読み手を引き付けることはできますが、その後に続く構成が難しくなります。自然な構成にできた読書感想文であるほど、高評価を得やすいでしょう。
自分の感情から入るパターンも、読み手を引き付けやすい方法です。表現された感情が激しいものであるほど、この文章を書いた人は何を感じ考えたのかということへの興味が湧きやすいでしょう。
コンクールで指定された過去の課題図書
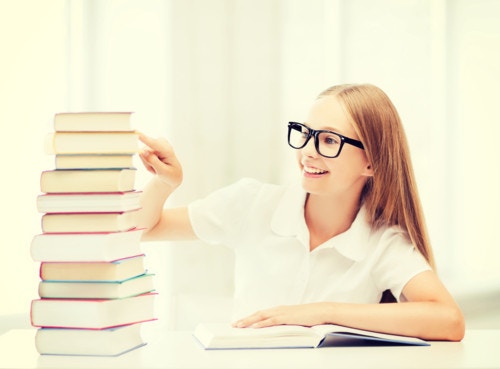

読書感想文コンクールで選出される課題図書は、どの作品も読んでいて心に残り、考えさせられるものばかりです。親しみやすいストーリーと、発見、感動を伴う内容となっている本が課題図書となっています。
読書感想文を書く目的で読むのはもちろんですが、その本をただ楽しむという意味で、いろいろな本を読んでみるのもおすすめです。
2022年の青少年読書感想文全国コンクールで小学生の部に選ばれた課題図書をご紹介します。
小学校低学年
小学校低学年の部における課題図書は、絵やストーリーの親しみやすさ、読みやすさを意識して選出されています。
つくしちゃんとおねえちゃん
つくしちゃんのおねえちゃんは、二つ年上の4年生。頭がよくてものしりでピアノも上手な自慢のおねえちゃんです。でも、ちょっと怒りっぽくていばりんぼうで、いじわるなときも…。
そんなおねえちゃんは歩くとき、少し右足を引きずるがんばり屋さん。大すきなおねえちゃんとの毎日の生活をつづった五つの物語。
ばあばにえがおをとどけてあげる
ばあばはこのごろ元気がない。年を取り笑顔が消えてしまったばあばを見て、「人生から喜びが消えちゃったみたい」と言うママの言葉を聞いた孫のファーンは、よろこび」って、なんだろう?と考え、ばあばのために「ワァーイ!」ってなることを探しに行くのでした。
「よろこび」の意味を教えてくれるお話です。
すうがくでせかいをみるの
パパは絵を描き、ママは虫の研究、おにいちゃんは音楽…家族はみんなそれぞれ好きなことがあるのに、私にはぴんとくるものがない。
でも、一つだけ「これだ!」と思ったのは、身の回りの数や形を見つけていろいろ考えることが楽しい「数学」だった。
一見難しそうな数学で楽しく世界を見ることのできる作品。
おすしやさんにいらっしゃい!:生きものが食べものになるまで
7人の子どもたちがおすし屋さんを訪れ、海から釣りあげられた魚や貝が包丁でさばかれおすしになるまでを写真で伝えていきます。
生きものが食べものになり、そして自分たちの体の一部になるということを実感させてくれる作品です。
小学校中学年
小学校中学年の部では、やや非日常的な生活の中でも身近なものとして捉えられる物語ばかりです。メッセージ性が強い作品が課題図書となっています。
みんなのためいき図鑑
ためいきってどんな時につくの?そんな疑問を持った4年生の「たのちん」こと田之上嵐太たちのグループは「オリジナル図鑑」として「ためいき図鑑」を作成することに。
ためいきをテーマに、家族や友達との関係に揺れる子どもたちの気持ちを描いた作品です。
チョコレートタッチ
ジョンはお菓子が大好きな男の子で、ごはんやおかずは残してお菓子を食べてしまうほど。
なかでもチョコレートには目がなく、ある日ひろったコインで買ったチョコレートを食べたジョンは、口に入れるものがすべてチョコレートになってしまい、大喜びしますが…。
子どもの心にいろいろなことを考えさせてくれるお話です。
111本の木
インドの大理石工場で働くスンダルさんは、村が荒れ地になっていくことを憂いて村長になるも、翌年娘を病で亡くし、村に女の子が生まれるたびに111本の木を植えてお祝いしようと提案します。
もともと村では女の子の誕生は歓迎されていませんでしたが、次第に森からの産物が安定収入となり村は発展していくのでした。
女性に学ぶ機会を与えた実話に基づく村長さんのお話です。
この世界からサイがいなくなってしまう:アフリカでサイを守る人たち
科学的な根拠はないのに薬になると角が高値で取り引きされるサイは、密漁によりその数が激減していた。
専門家は「あと20年でアフリカからサイがいなくなってしまうかもしれない」と懸念し、サイを守るためにさまざまな取り組みが行われるのだった。
南アフリカ共和国での取材を行ったNHK記者によるノンフィクション作品。
小学校高学年
小学校高学年の部の課題図書では、死生観や社会問題など、大人でも迷うことのある現実での重いテーマを扱ったものが目立ちます。
また、子どもたちが自分の恐れるものに立ち向かい、弱さを克服していく成長物語など、読んでいる子ども自体に考えさせる内容で、子どもだけでなく大人にとっても読み応えのある作品ばかりです。
りんごの木を植えて
小学5年のみずほは、二世帯住宅で暮らしている祖父の病気が進行しており、祖父は入院治療を拒んでいることを知る。
自分の思うように生きて満足して死にたいと願う祖父に寄り添いつつ、みずほは祖父がつぶやいた「たとえ明日、世界が滅亡しようとも、今日わたしはりんごの木を植える」の言葉の意味を考えるのだった。
生きること、死ぬことを考えさせてくれるお話。
風の神送れよ
長野県伊那谷には、疫病退散を願ってすべてを子どもたちだけが行う「コト八日行事」という400年続く国の無形文化財がある。
来年は中学1年生として頭取となる優斗は補佐役を務めていたが、頭取が足を骨折し参加できなくなってしまい…。
仲間と困難に立ち向かいながら成長していく子どもたちを描いた作品。
ぼくの弱虫をなおすには
小学4年生のゲイブリエルはこわいものがたくさんある弱虫な少年。特に、5年生となって自分をいじめる上級生と同じ校舎になることを一番こわがっていたが、親友のフリータと共に「こわいものリスト」を作り、困難を乗り越えようとしていく。
人種や生活の違いを超えて協力しながら、子どもたちが困難に立ち向かう姿を描いた本。
捨てないパン屋の挑戦 しあわせのレシピ
町のパン屋に生まれた田村さんは、流行りの菓子パンを作る職人が「にせもの」に思え、修行中のパン屋から逃げ出し放浪の旅へ。
その先でたどり着いたのは、まき窯で焼く天然酵母の「ほんもの」のパン作りだったが、たくさん売れ残ったパンは捨てるしかなく、「捨てないパン屋」を目指すことに。
捨てないパン屋として評価される田村陽至氏の思想を描いたノンフィクション。
低学年からコンクールにチャレンジしてみよう


読書感想文コンクールは、参加するならぜひ入賞をと考えてしまいますが、テーマ性のある本を熟読し、自分なりの考えをまとめて文章として表すこと自体が、子どもにとって非常に大きな成長を促してくれるものです。
入賞するためのテクニックも今後の文章作成に役立ちますが、決められた本を読み切って感想文を完成させたことが大きな自信につながるでしょう。
今回紹介した課題図書はどれも読み応えがあり、それぞれの小学生の学年に合わせて新たな知識や見識を広めてくれるものばかりで、感想文を書かなくても読むだけで価値のあるものです。
感想文を苦手とする子もいますが、まずは低学年の子どもにもぴったりな課題図書を読んでみることから勧めてみてはいかがでしょうか。